サイバーコミュニティ研究部門
Cybercommunity Division
(http://www-dg.setc.wani.osaka-u.ac.jp/keitai/)
1 部門スタッフ
教授 阿部 浩和略歴:1983年3月大阪大学工学部建築工学科卒業、同年4月(株)竹中工務店入社、1996年4月(株)竹中工務店設計部主任、1998年4月(株)竹中工務店 設計部課長代理、1998年4月大阪大学全学共通教育機構非常勤講師(兼務)、2002年4月大阪大学講師サイバーメディアセンターサイバーコミュニティ研究部門、2003年10月大阪大学助教授サイバーメディアセンターサイバーコミュニティ研究部門、2004年10月大阪大学教授サイバーメディアセンターサイバーコミュニティ研究部門、日本図学会、日本建築学会、ISGG各会員。
講師 寺田 努
略歴:1997年3月大阪大学工学部情報システム工学科卒業。1999年3月大阪大学大学院工学研究科情報システム工学専攻博士前期課程修了。2000年6月大阪大学大学院工学研究科情報システム工学専攻博士後期課程退学。2000年6月大阪大学助手サイバーメディアセンターサイバーコミュニティ研究部門助手就任。2005年1月より同部門講師。IEEE、情報処理学会、電子情報通信学会各会員。
2 教育および教育研究支援業績
本研究部門の教育に係わる主な活動を、以下に列記する。2.1 教育活動
本部門は大学教育実践センターにて図学教育を、工学部建築工学科、工学研究科建築工学専攻にて建築・都市形態工学講座を兼任しており、学部、大学院の学生の研究指導を行うとともに、下記の講義を担当した。大学教育実践センター
- 図学B‐Ⅰ
- 図学B‐Ⅱ
- 図学実習B‐Ⅰ
- 図学実習B‐Ⅱ
- 問題を解くための可視化と図表現
- 景観論
- パソコンによるコンピュータグラフィックス入門
- 建築設計第4部
- 建築形態工学
- 建築形態工学演習
- 建築形態工学特論
- 建築空間生理学
- 建築工学特別講義Ⅰ
- 建築工学ゼミナールⅠ
- 建築工学ゼミナールⅡ
2.2 スペースコラボレーションシステム(SCS)運営
SCSの大阪大学内VSAT局大阪3の運営責任者を務めると共に、大学、関係部局が実施するSCSを用いた授業及びシンポジウム(以下に記す)について、VSAT局の操作支援を行った(阿部)。- ボランティア論(教育実践センター特別科目)
- 問題を解くための可視化と図表現(教育実践センター特別科目)
- 英文学会シンポジウム(文学部主催)
- SCS活用セミナー2004(独立法人化メディア教育開発センター主催)
- 企業人派遣講座特別講義(産学バーチャルユニバーシティーコンソーシステム主催)
- 企業人派遣講座特別講義(産学バーチャルユニバーシティーコンソーシステム主催)
2.3体験的課題追求型教育科目構築プロジェクト
同プロジェクトの一環として特別科目「マルチメディア時代の図学」を体験的課題追求型教育科目構築プロジェクトにおける体験的課題追求型授業として実施するとともに、専門基礎教育科目「図学実習B-Ⅰ」「図学実習B-Ⅱ」を体験的授業として実施し、当該WGの委員を務めた(阿部)。3 研究概要
サイバーコミュニティ研究部門では、情報化技術に支援されるコミュニティの構築に関する研究を行う。具体的には情報ネットワークによって統合される都市・建築群・組織・個人の枠組みにおけるコミュニティの構築と建築群の形態構成過程のマネジメント最適化に関する課題、及びその間で取り交わされる伝達情報としての図的表現法とその認知の的確化に関する課題などを取り扱う。現在、本研究部門では、以下の研究課題に取り組んでいる。3.1 SCSなどの遠隔教育の企画運用と体験型授業に関する研究
SCSは、Space Collaboration Systemの略で、通信衛星を利用して大学間を結ぶ情報通信ネットワークの名称である。1996年10月から試験運用が開始され、1997年4月からは運用が始められた。このシステムの端末が設置された講義室をVSAT(Very Small Aperture Terminal)局と呼ぶが、VSAT局間では映像や音声を双方向にリアルタイムで交換できるため、複数のVAST局どうしを結んで講義や研究会、会議を行うといった使い方が可能である。当研究部門では1996年度から北海道大学、東京大学、名古屋大学間をSCSで結び、一般図形科学を内容とする共同講義を実施してきており、2003年度からは体験的課題追求型授業として受講生が実際にSCS機器を使って互いにコラボレーションを行う授業形式を取り入れている。当研究部門では今後、これまでの実績をもとに、インターネットを用いた遠隔講義やe-Learningなどにも対応したコースウェアとコンテンツの開発・研究を進める。
3.2 建築形態構成過程における建築主と設計者との合意形成の的確化に関する研究
サイバーコミュニティを収容するハードウェアとしての都市環境や建築群の構築には、高度化、専門化した知識が必要となり、これまで設計者に全てを任せることができた時代は終わり、包括的、統合的なプロジェクトマネジメントが不可欠になってきている。また一方で、公的規制の緩和に伴い、企業の自己責任原則の強化とアカウンタビリティの必要性が指摘されてきている。本研究部門は、このような観点から、建築プロジェクトの企画から設計、施工にいたるプロセスをコミュニティの形態構成過程と捉え、設計マネジメントの現状をクライアントとのかかわりの中で見直すことで、その設計討議における合意形成過程の適正化に関する知見を明らかにするとともに、コミュニティ構築のためのプロジェクトマネジメント手法の開発を行う。3.3 建築物の大規模災害時におけるマルチエージェント型シミュレーションシステムの開発
近年の急激な都市化とともに、建物の地下利用が増加し、地下空間は深層化、複合化の方向に向かっている。また同時に、今後発生が予想される大地震など未曾有の都市災害に対する地下空間の危険性も指摘されている。一般に地下空間の安全性の確保には、(1)火災・爆発、(2)地震、(3)浸水、(4)停電、(5)救急・救助活動、(6)犯罪防止について対策を講じる必要があるとされるが、その中でも浸水災害の事例として、1999年6月の博多駅周辺での集中豪雨による冠水事故や、同年7月に東京で発生したビルの地下室での溺死事故、2000年9月の東海での浸水事故、2003年7月の福岡での浸水事故などがある。さらに今後起こると予測されている東南海、南海沖地震による津波は、都市の地下空間を浸水させ、大きな被害をもたらすと危惧されている。本研究部門ではこのような危機管理性能の弱点が多く残されている大都市の建築群における地下空間のリスクマネジメントプログラムの開発を進めるとともに、大規模災害時のマルチエージェント型シミュレーションとユビキタスコンピューティングに基づく避難誘導システムの開発を進めている。3.4 汎用可視化システムの開発とVR装置への適用性
リアルタイムCGは、コンピュータが3次元コンピュータグラフィックスを実時間で処理し、連続的に画像化する技術で、近年、これを実現するGPUの進歩は著しく、フォトリアリスティックなCGがリアルタイムで表現できるようになった。これまで建築防災の分野では、VRMLによりリアルタイムで可視化した仮想空間で避難シミュレーションを実現した事例や、被験者が画面上の避難者を操作することで災害を疑似体験し危機管理教育に適用する研究が行われているが、再現される画像の精度やモニターなどの装置によっては臨場感に欠けることも考えられ、十分な疑似体験を提供できない可能性も考えられる。本研究部門では、高速リアルタイムCG技術をVRシミュレーションへ適用し、没入型可視化システム(CAVEシステム)で再現可能な汎用的可視化システムの開発行う。3.5 開発途上国における建築群形態構成と保全に関する研究
東南アジアにおける都市化現象は、都市の社会基盤を上回る労働人口の過剰流入によって居住環境の悪化をもたらしている。その中でも社会主義からの政策転換から間もない後発発展途上国であるラオス人民民主共和国において、顕在化しつつある都市化現象を地域コミュニティ構築の観点から調査分析することで、住空間計画の実効性向上に資する要件を追求する。またそれとともに、長い間培われてきたラオスの特徴的住生活様式、伝統的建造物の保全に関する問題は、ラオスの古都ルアンプラパンがUNESCOの世界遺産に登録されたことなどからも、世界の注目を浴びており、多くの外国人観客や外国資本の流入とともに、伝統的建造物群や生活文化の保全とその維持保全システムの研究が欠かせない。当研究部門ではこのような観点から発展途上国のコミュニティ構築と建築形態構成の最適化に向けた研究を行う。3.6 図的表現法と読図能力に関する研究
図学教育を取り巻く環境は、近年の情報化技術の進展とともに大きく変化してきている。中でもオブジェクト指向の3DCADツールとそれに連動した制作装置の出現によって、コンピュータ上でバーチャルにイメージしたものが、そのまま実物としてアウトプットできるようになってきており、個々の部品に属性を付けることで3Dデータと実物が1対1の関係になりつつある。しかし一方で建築の専門教育の現場からは図形化力や空間認知力の欠如といった学習障害の問題や、スケール感の欠如、原理にもとづかない不自然な透視図の増加、読図能力の低下などの問題が指摘されはじめている。これらはCAD化に伴う3次元空間や立体物の認識プロセスの変化とそれらの情報を正確に加工伝達できる能力の欠如からくるものであり、新しい情報化技術に対応した図法幾何学や空間幾何学の教育が必要であることを示唆している。本研究部門では、こうした観点から、3次元形態の図的表現法とその読図能力に関する研究を行う。3.7 建築設計教育と設計課題設定に関する研究
近年、建築設計教育を取り巻く状況は、建築家資格の国際同等性の議論を契機に、建築分野におけるJABEE認証制度の開始や、建築学会による設計教育のあり方についての提言、実務的教育導入の問題など、これまでのわが国における建築設計教育に対する様々な議論がなされ始めている。1999年のUNESCO/UIAの総会で採択された建築設計者資格の国際的な推奨基準においては、「大学レベルにおける5年以上の教育」や「半分以上の時間をスタジオ教育に当てること」、「アクレディテーションの実施」、「実務教育の充実」などが見られ、これまでのわが国の建築教育の現状と整合しにくい要件が示されている。本研究部門では建築家資格の国際的同等性を主張する上で最も重要とされる建築設計教育に関する研究を行う。3.8 建築および建築群の形態構成に関する研究
建築および建築群の構築とその形態構成には、その時代の社会システムや制度、様々な法規制の影響を受け、施設そのものが持つ機能やイメージとは別の制約を受けざるを得ない。例えば2004 年2 月に閣議決定された景観緑三法は我が国で初めての景観についての総合的な法律であり、これまで法的な強制力のなかった自治体の景観条例に対して、その背景となる法律が整備されたことになるが、その影響や効果は今後評価されることになると思われる。本研究部門ではこのような建築形態にかかわる社会制度を取り上げ、建築および建築群の形態との関連性を分析することで今後の制度設計の最適化のための研究を行う。
3.9 高度なコミュニティ形成を実現するウェアラブルコンピューティングシステムに関する研究
携帯端末の小型化・軽量化に伴って、ユーザが計算機を身につけて持ち運び、場所にかかわらずに計算機を利用するウェアラブルコンピューティングに対する注目が高まっている。ウェアラブルコンピューティングはハンズフリー・常時オン・生活密着といった特徴をもち、GPSや磁気センサなど各種のデバイスを柔軟に組み合わせてユーザの生活をサポートするさまざまなサービスが要求されている。しかしこれまでのシステムでは、場所に応じて機能を動的に変更するといった柔軟性がなかったり、使用するデバイスが固定されているという問題があった。そこで、本研究ではアクティブデータベースの概念を用いることで機能のカスタマイズや各種デバイスの追加・変更を容易にするウェアラブルコンピューティングの基盤システムを構築する。提案システムにより、ウェアラブルコンピュータを活用した新たなコミュニティの実現が期待できる。3.10 ユビキタスコンピューティングを実現するイベント駆動型小型デバイスに関する研究
近年のマイクロエレクトロニクス技術の発展や、PDAや情報キオスクなどさまざまな形態のコンピュータの普及により、いつでもどこでもコンピュータにアクセスできるユビキタスコンピューティングに対する注目が高まっている。ユビキタスコンピューティング環境ではいたるところにコンピュータが存在し、コンピュータ同士またはコンピュータとユーザが持つ端末とが連携することでさまざまなサービスを提供する。しかし、現在提案されているシステムは互換性がなく、また専用端末であるために汎用性、コスト面での手軽さに問題を抱えている。そこで、本研究では安価に多用途で利用できる汎用ユビキタスコンピュータに関する研究を行っている。提案するユビキタスコンピュータはその動作をECAルールと呼ぶ動作記述言語で記述するため、ルールを入れ替えることでさまざまな用途に利用可能である。また小型・軽量であるため、いたるところに組み込まれるユビキタスコンピュータとしての手軽さ、低コスト性を実現している。3.11 コミュニティにおけるコンテンツ管理を実現する情報フィルタリング・問合せ処理技術に関する研究
広帯域放送サービスやモバイル環境におけるブロードバンドサービスが普及するにつれて、ユーザが受信する情報量は膨大になっている。そのような環境においては、ユーザが大量の受信情報から自分に必要な情報を取得するためには情報フィルタリングの技術が重要になる。これまでにもさまざまな情報フィルタリング手法が提案されてきたが、それぞれの手法を定性的に評価する枠組みが存在していなかった。そこで本研究では、情報フィルタリングを関数として表現し、フィルタリングの性質を関数が満たす条件として定義する。各性質間の関係や合成関数の性質を明らかにすることで、フィルタリングアルゴリズムを定性的に表現でき、フィルタリングシステムの性能比較や等価なフィルタリングアルゴリズムへの置換が可能になる。また、性質関係や合成関数の性質を用いて、フィルタリングシステムの処理の最適化や、複数のフィルタリングシステムを合成した場合の処理の等価性を評価できる。さらに、提案方式を備えたフィルタリングシステムや放送型データ処理システムを実装することで、新たなコミュニティ形態における情報処理技術の提案を行っている。3.12 屋外における音楽活動を支援するシステムに関する研究
近年のモバイルコンピューティング技術の発展により、人々は屋外でもコンピュータの支援を受けられるようになった。このようなコンピュータの支援は、人々の生活やコミュニケーション手段を変革させるポテンシャルをもっている。そこで、本研究では特に音楽活動に注目し、屋外で自由に音楽活動が行えるようなシステムを構築することで、音楽による自己表現やコミュニケーションを可能とする環境を実現することを目指している。4 2004年度研究業績
4.1 SCSなどの遠隔教育の企画運用と体験型授業に関する研究
これまで大阪大学、東京大学、北海道大学の3大学は、大阪大学をホスト校として、SCS(スペースコラボレーションシステム)を用いて共同講義「マルチメディア時代の図学」を一般の学生を対象に実施してきた。その内容はこれまで工学系で扱っていた図法幾何学を図に関するリテラシーという観点で初心者向けに構成したもので、遠隔地間の各大学における教官がその専門分野をそれぞれの大学の受講生に講義し、受講生が質問するといった双方向の講義形態をとっている。本年度は「体験的課題追求型授業(北海道大学では創成型教育)」として「問題を解くための可視化と図表現」という科目で実施した。これまでは各大学の教官側からそれぞれの大学の受講生に講義を行い、それに対する質問に答えるといった双方向の講義形態であったが、今回は遠隔地間の学生を混合したグループワークを取り入れ、受講生自身にSCSを使ってコラボレーションをさせることを試みた結果、学生の満足度の向上が見られたこと、日ごろ何気なく見過ごしていた身の回りの環境について問題意識を持たせる契機になったこと、しかし限られた時間内でのSCSによるコミュニケーションに限界があること、などの知見が得られた。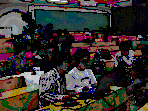
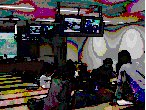
図1-1 授業風景(マルチメディア時代の図学)
関連発表論文
(1) Hirokazu Abe, Somchith Sitthivan, Kensuke Yasufuku and Katsuyuki Yoshida,“Application of New Method for Graphic Science Education”, Proceeding of The 11th International Conference on Geometry and Graphics, pp293-298, August 2004.4.2 建築形態構成過程における合意形成の的確化に関する研究
設計図面は、設計段階における当事者間の共通言語であり、打合せの結果完成された設計図書は、施主のニーズが的確に反映されていると同時に、施工者への情報伝達機能も十分に満足するものでなくてはならない。ここでは、実際に施工された建築プロジェクトを調査対象とし、実施の建築プロジェクトにおける設計完了時点の設計図面の「書き込み不足」が施工段階の設計変更に影響しているかどうかを明らかにすることを目的に、積算段階の見積質問書と施工段階の設計変更リストの分析を行った結果、設計が完了した設計図面においても、仕上工事における「材種、材質」や「寸法」などの「書き込み不足」や「図面間の食い違い」が存在すること、設計図面に対する見積指摘率は、仕上表(内部)が最も高いこと、施工段階で発生した設計変更は仕上工事における「形状」、「仕様・その他」に関する内容が多いこと、平面詳細図や平面図など平面系図面は、見積指摘率、図面変更率ともに高いこと、仕上表については、見積指摘率が高いが、図面変更率は低く、展開図に関しては、図面変更率が高いが、見積指摘率は低いこと、プロジェクトの見積質問書と設計変更リストのそれぞれの記述内容において共通する部位が約13%存在することなどが明らかとなった。関連発表論文
(1) 阿部 浩和,吉田 勝行,“建築設計図面に対する見積指摘内容と設計変更内容の関連,”日本建築学会,日本建築学会計画系論文集No.581号,pp49-54, 2004.74.3 建築物の大規模災害時におけるマルチエージェント型シミュレーションシステムの開発
地下空間浸水時の個々の建築空間における個々の避難者を扱った避難シミュレーションシステムを開発し、国土交通省の告示にある避難安全検証法との比較を行った上で、地下空間浸水事故の事例にあてはめ、地下空間浸水時の適用性を評価した結果、居室避難時間においては、その居室の出口と、そこを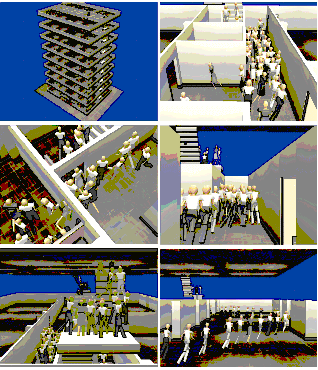
図1-2 シミュレーション画面
出た次の出口の位置関係によって差はみられるものの、階避難安全検証法に見込まれる安全率を考えれば概ね一致すること、全館避難時間には幾分差がみられること、地下空間浸水事例に関しては改修後のB室では全員が避難できなかったこと、また改修前では全員が避難できたことなどから、改修工事により地下空間浸水時の避難安全性能が低下したと推察でき、地階室の間仕切りの配置には、浸水時の避難安全性の検討が不可欠であるという結果が得られた。
関連発表論文
(1) 安福 健祐,阿部 浩和,山内 一晃,吉田 勝行,“避難シミュレーションシステムの開発と地下空間浸水時の避難に対する適用性”,2004年度日本建築学会(北海道)学術講演梗概集,No5425、2004.8(2) 安福健祐,阿部浩和,吉田勝行,“リアルタイムCGによる汎用可視化システムの開発-マルチエージェント型建築避難シミュレーションへの適用-”,2004年度日本図学会本部例会学術講演論文集,2004.12
4.4 汎用可視化システムの開発とVR装置への適用性
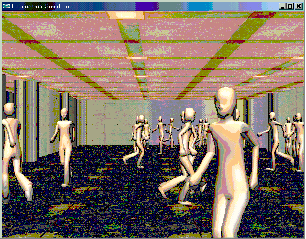
図1-3 建築避難シミュレーションの可視化
CAVEシステム(没入型ディスプレイ)を使ったVR装置に適用できる汎用性を重視したリアルタイムCGによる可視化プログラムを開発し、建築避難シミュレーションにおける人の動きの可視化実験を行った結果、特定のPC上では、112,304ポリゴンを10fpsで可視化できること、CAVEシステムでは、112,304ポリゴンを2fpsで可視化できることなどの結果を得、一般PC(WINDOWS)とCAVEシステム(UNIX)という2つの異なるハードウェア及びOSにおいてリアルタイムCGで実現できる汎用的な可視化システムの基本部分が開発できたことが確かめられた。
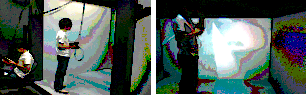
図1-4 没入型ディスプレイによる実験
関連発表論文
(1) 安福 健祐,阿部 浩和,吉田 勝行,“汎用可視化システムの開発とVR装置への適用性”,日本図学会関西支部例会学術講演論文集,2005.24.5 開発途上国における建築群形態構成と保全に関する研究
4.5.1 ルアンプラパンの歴史的遺産保存地区におけるPSMVの現状と課題
ルアンプラバンにはラオスの伝統文化の独自性を示す古くからの建造物や景観が数多く残っており、その街並みは1995年にUNESCOの世界遺産に登録されている。またそれに伴いラオス政府はUNESCOの協力を得て、建築物や景観、自然環境の保存に関する規則を設け、その保全に取り組んできた。しかしその後の調査において、現状ではこのような規則がまだ十分に守られていないという報告がある。そこでPSMVの現状と問題点を把握するため、2003年6月から7月までの間、ラオス国立大学建築学部の協力を得てUNESCOの現地調査に同行するとともに、その調査結果を分析した結果、違反建物の指摘件数はZPP-Ua地区とZPP-Ub地区がその大半を占めており、その建築用途は大半が住宅用途であること、違反の大半を占めるZPP-Ua、ZPP-Ub地区の住宅用途の建物に関する違反内容は、新築工事では屋根の色の違反や全体のボリュームに関する違反の割合が多く、改築では屋根の形態や外壁の材料に関する違反の割合が多いこと、違反建築物における許可申請の状況は全体の86%が申請を行っておらず、その割合は2002年に対して2003年でやや増加していること、許可申請によってZPP-Ua地区では屋根形態の違反や全体ボリュームの違反の割合が減少するがZPP-Ub地区ではあまり減少しないこと、また1階建ての建物については、許可申請によって屋根形態、色の違反の割合が減少するが、2階建ての建物については屋根の材料の違反の割合が減少しないこと、許可申請を行っているにもかかわらず違反指摘がある建築物に関しては、許可申請図どおりに工事されていないケースが多く見られること、設計や施工を行うのが建築の専門家ではない一般住民であるために、政府が策定したPSMVの規則が十分に理解されていない可能性があることなどの結果を得ている。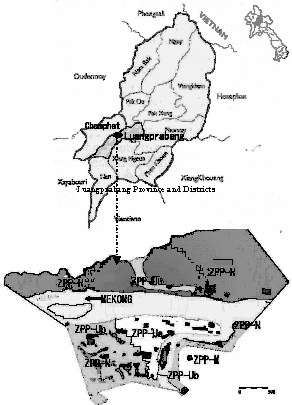
図1-5 ルアンプラバン市歴史的遺産保存地区(PSMV)
関連発表論文
(1) Sitthivan Somchith,河本 順子,阿部 浩和,“ルアンプラパンの歴史的遺産保存地区におけるPSMVの現状と課題”,2004年度日本建築学会近畿支部研究報告集,第44号・計画系,pp821-824、2004.64.5.2 ラオス及びタイ中北部におけるテラワダ仏教寺院の平面構成要素に関する研究
ラオスの伝統的寺院建築の特徴を明らかにするため、ラオス及びタイ中北部の仏教寺院におけるプッタシマの平面構成要素を地域別に分析した結果、タオシムの柱間の数はホンロイが3である場合が75%で最も多く、ホンクアンの数は4~5である場合が全体の約半数を占めること、タオシムの前面、後面における柱の断面形状について、壁に囲まれる形式の柱はラオスのシェンクアン、タイのアユタヤの寺院に多く見られ、ニョームーム形の柱はヴィエンチャンの寺院にのみ見られること、また円形や八角形の柱はタイのチェンマイにおける前面の柱にみられ、その他の地域ではあまり見られないこと、タオシムの柱と壁の取り合いの状況は、シェンクアン、アユタヤでは、その80%以上が壁の中に柱が取り込まれており、柱が内側にのみ出ているケースはヴィエンチャンに多く、内側、外側いずれにも出ているケースはチェンマイのプッタシマの前面に多く見られること、プッタシマにおける「側面、前面での柱と壁の取り合い」や「側面での柱の形状」、「ホンクアン(奥行方向)の柱間数」などによってラオスとタイ中北部の寺院建築特徴の違いが判別されることなどの結果を得ており、ラオスの伝統的建築の独自性を明らかにする手がかりが得られた。
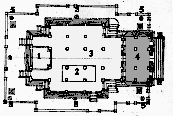
図1-6 ワット・シェントンの外観と平面
関連発表論文
(1) スーカン チッパンニャー,河本 順子,阿部 浩和,吉田 勝行,“ラオス及びタイ中北部におけるテラワダ仏教寺院の平面構成要素”, 日本建築学会,日本建築学会計画系論文集No582号, pp41-16, 2004.84.5.3 ヴィエンチャン市における集合住宅の現状と住まい方に関する研究
ラオスの都市住宅の今後のあり方を考えるために、ヴィエンチャン市における先駆的な集合住宅について実地調査を行った結果、アパート形式のプランタイプ原型の全体平均面積は81.1㎡、台所平均面積12.5㎡、便所・風呂等平均面積5.6㎡、廊下他平均面積3.6㎡、居室平均面積47.0㎡、ベランダ平均面積12.4㎡であること、現在住んでいる集合住宅の室規模について、居住者の希望は、室面積を現在より大きくとりたいという希望が最も顕著なのが台所と食堂、次にベランダと居間で、寝室とトイレについては約半数が現状でほぼ満足としていること、広間には、応接セット、食卓、及びTV等数多くの家具が置かれるものの中央部に家具の置かれていない空きスペースが見られること、就寝方向について、アパート形式では、棟に垂直に就寝する居住者は全体45%で、長屋の70%に比して低いことなどの結果を得ている。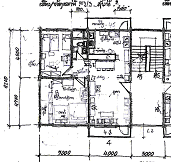

図1-7 アパートにおける住まい方の一例
関連発表論文
(1) パタナ ポンティップ,河本 順子,阿部 浩和,吉田 勝行,“ヴィエンチャン市における集合住宅の現状と住まい方”,日本建築学会,日本建築学会計画系論文集,No.585号, pp1-8, 2004.114.6 図的表現法と読図能力に関する研究
建築のような身体を覆う大きな空間の把握能力を計測するための手がかりを得る目的で、建築平面図読図テスト(以下PIT)を開発し、建築の専門教育を受けていない学生と建築設計を職業とする建築の専門家を対象にPIT及びMCTを実施し、両者の比較を通して、建築図読図能力の違いを分析した結果、後者の成績は前者の成績に比べて有意に高いこと、また前者においては外観設問の正答率が内観設問の正答率に比べて有意に低いのに対して、後者においては外観設問の正答率と内観設問の正答率の間に有意差は見られないことなどが明らかとなった。また同様のテストをラオス国立大学の学生176人とスファノウォン大学の学生53人を対象に適用した結果、 MCTに関してはNUOLのFCS2-Lの成績が最も高く、次いでFCS1-L 、SPHのFCS1-Sの順であること、PITに関して、ラオスのNUOLのAECS1の成績は日本のFCS1-Jの成績とほぼ同じである一方、ラオスのAECS1以外の成績は有意に低く、特にFCS1-Sの成績が低いこと、PITの平均点が高いAECS1とFCS1-Jにおいては外観設問が内観設問に比べて難しく、PITの平均点が低いその他のグループにおいては内観設問も外観設問もいずれも同様に難しいこと、ラオスのAECS1以外のグループとFCS1-Jにおいては2層設問が1層設問に比べて難しいのに対して、ラオスのAECS1は2層設問が1層設問に比べて難しくないことなどの結果を得た。
関連発表論文
(1) Sitthivan Somchith, Anolac Vira, Abe Hirokazu,“Laotian Visualization Ability for Architecture”, Proceeding of The 11th International Conference on Geometry and Graphics, pp274-278,August 2004.(2) Sitthivan Somchith,阿部 浩和,“ラオス人の空間認識力に関する研究”,日本図学会関西支部例会学術講演論文集,2005.2
4.7 建築設計教育と設計課題設定に関する研究
大学工学部3年生の建築設計演習の初期段階における具体化のプロセスを分析することで、当該学生にとって課題提示から1週間では、初期の基本構想イメージを確立するのが難しいこと、さらにその形態にかかわる作図やスケッチなどをあまり行っていない可能性があること、全設計期間7週の内、初期の4週間での結果としては、課題内容の把握から検討を経て具体的なイメージに収斂させていく作業に問題があること、機能図や断面構成図にかかわる検討はその後の草案作成にも影響を及ぼすことなどの結果が得られた。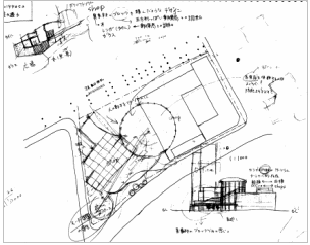
図1-8 設計演習の草案の一例
関連発表論文
(1) 山内 一晃,阿部 浩和,“大手総合建設会社の新社員に対する建築設計教育の概要”,2004年度日本図学会本部例会学術講演論文集,2004.12(2) 阿部 浩和,吉田 勝行,“設計演習の初期段階における具体化のプロセスに関する一考察”,日本建築学会,第5回建築教育シンポジウム論文集,pp81-86,2005.1
4.8 建築および建築群の形態構成に関する研究
4.8.1 住民意識から見た都市景観の構成に関する研究
ここでは日本の中核都市として姫路市を取り上げ来訪者側から見た姫路市の実態が行政の取り組みとして表れているか、また行政の取り組みが住民の景観評価として表れているかを明らかにするため行政へのヒアリングと市民へのアンケートを実施した結果、来訪者に対する施策としては姫路城周辺および大手前通りの魅力づくりが重要であると考えられること、行政は早くから広告物の指導という形で景観づくりに取り組んでいるにもかかわらず、条例規制の建築物への適用件数が少なく、そこでの活動が多い住民の景観評価からはその取り組みが十分に表れていない可能性があることなどの結果を得た。関連発表論文
(1) 田口 ゆか, 阿部 浩和,“住民意識から見た都市景観の構成に関する研究‐姫路市を事例として‐”,2004年度日本建築学会近畿支部研究報告集、第44号・計画系,pp753-756,2004.6(2) 田口 ゆか,阿部 浩和,“住民意識から見た都市景観の構成に関する研究”,2004年度日本建築学会(北海道)学術講演論文集,No.7504,2004.8
4.8.2 総合衛生管理製造過程(HACCP)が適用される食品工場の建築計画に及ぼす影響
これまで、社会における大規模の食中毒事件の原因が食品製造施設等の製造過程に関する問題が多いと指摘されていることから、食品工場の製造施設や製造過程等における衛生管理の強化とそのために必要な建築計画の適正化が必要になってきている。ここでは食品の安全性を確保するために食品の衛生管理手法であるHACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points)が適用される食品工場を調査・分析することで、食品工場の清潔作業区域は年代とともに増加していること、日本においてHACCP は1995 年に改正されているが、1970 年を境に衛生管理区域の出現率が増加すること、工場内の物品の動線は年代やHACCP にかかわりなく、殆どがワンウェイで構成されていることなどが明らかとなった。関連発表論文
(1) Boutdakham Thanomxay, 阿部 浩和,“総合衛生管理製造過程(HACCP)が適用される食品工場の建築計画に及ぼす影響”,2004年度日本建築学会(北海道)学術講演梗概集,No5135、2004.84.9 高度なコミュニティ形成を実現するウェアラブルコンピューティングシステムに関する研究
近年、マイクロエレクトロニクス技術の発展による計算機の小型化・軽量化に伴って、ウェアラブルコンピューティングに対する注目が高まっている。ウェアラブルコンピューティングとは、計算機をユーザが常に身に付けて持ち運ぶコンピューティングの一形態であり、従来の計算機の利用形態と比較して次の3つの特徴をもつ(図2-1)。・ハンズフリー:コンピュータを身体に装着しているため、常に両手が使用できる。
・生活密着:常にコンピュータを装着した状態で、日常生活を行う。
・常時オン:コンピュータは常に電源が入っており、使いたいときにすぐに使える。
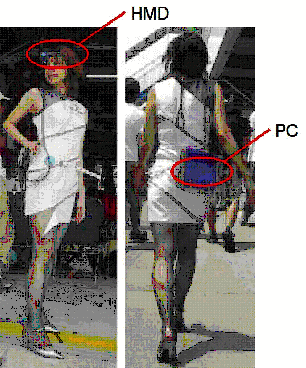
図2-1 ウェアラブルコンピューティング
ウェアラブルコンピュータはハンズフリーで利用できるため、ユーザは他の作業を行いながら、マニュアルなど各種の情報を閲覧できる。また、計算機の電源が常に入っているため、ユーザが計算機を利用していないときにも情報を収集することが可能となる。さらに、計算機はユーザとともに移動するため、現在位置に関する情報を取得しながらナビゲーションを行ったり、ユーザが会社にいる間はプライベートなメールの受信を停止するといったサービスが提供できる。ウェアラブルコンピューティング環境では、ユーザは常に個人用端末を携帯して行動するため、目的によって機器やシステムを取り替えるのではなく、場所や目的に応じて端末の機能を柔軟に変更できることが望ましい。そこで本研究では、ウェアラブルコンピューティング環境において、各種センサやデバイスの状態を処理し、様々なサービスを提供するための基盤システム「A-WEAR」に関する研究を行っている。A-WEARは、各種の入力を処理するルールによって、ウェアラブルコンピューティング環境における様々なサービスを提供する。また、プラグインメカニズムを用いることで動的なシステム拡張を実現している。これまで、基本的なシステム設計およびプロトタイプの実装を行ってきたが、本年度はA-WEAR自体の機能拡張を継続的に行うとともに、実用化に向けての取り組み、ルールベースのシステムを安全に運用するための枠組みに関する検討を行った。
実用化に向けての取り組みとしては、A-WEARのさまざまな応用システムを開発し、実際に利用することで実証データの収集およびシステムの有効性の確認を行った。具体的には、昨年度も行ったバイクレースのピット作業をサポートするシステムをさらに拡充し、2004年8月に行われた鈴鹿8時間耐久ロードレースで実際に使用した。このシステムはヘッドマウントディスプレイ(Head Mounted Dis-play: HMD)上に、チームに所属する選手の周回情報や順位、ライバルとの位置関係などをリアルタイムで提示し、さらにピットインが必要なタイミングを指示するといった機能をもつ。2004年度のシステム構成図を図2-2に示す。システムは、サーキットのコントロールタワーがFM波で配信しているラップ情報をピット内に設置したサーバで受信し、順位や燃料の残量、周回数を計算して無線LAN経由でウェアラブルコンピュータに配信する。システムはチーム監督やピットクルーのためのものであるが、2004年度は観客向けのシステムも開発してデモ運用した。コース内にはレポータスタッフを多数配置し、事故やレース状況をデジタルカメラで撮影させ、その他の情報と共にサーバから配信した。図2-3は戦略立案画面、図2-4はコース画面、図2-5は掲示板画面である。ユーザごとに閲覧できる情報は異なり、例えば監督は戦略立案画面およびコース画面を閲覧でき、観客は掲示板画面およびコース画面を閲覧できる。システムを利用している様子を図2-6に示す。
戦略立案画面ではラップ情報がリアルタイムに表示され、前後のチームやトップチームとの差を常に把握できる。また、中央部はライダー交代の予想タイミングを表示している。バーの位置はライダーの違いを表しており、図では6回のライダー交代をすでに終えており、現在第一ライダーがあと8週走れることを示す。これらの値は給油量、平均燃費から自動的に計算され、急なピットインなど状況の変化に応じてリアルタイムに更新されるコース画面は戦略立案画面の中央部をコース図に置き換えたもので、現在の各バイクの位置をリアルタイム表示している(実際は1周前の情報をもとに予測している)。また、重要な情報は写真つきで配信される。掲示板画面は、レポータからのコメントつき写真を掲示板のように閲覧できる画面で、撮影地点も画面上に表示される。
チーム監督はほぼ8時間にわたり大きなトラブルなくシステムを利用し、総合18位というレース結果を残すことができた。監督のコメントから得られた知見としては、HMDのような個人ディスプレイは他のチームに知られたくない情報を提示するのに有効であり、また、他の活動を行いながら情報閲覧ができるため、レースのように情報戦を行う用途に適していることがわかった。また、観客向けのサービスに関しては、これまで来場者が得られる情報があまりにも少なく、サーキットが掲示する情報も上位チームに限られていた。そのため、レース観戦自体を邪魔することなく、リアルタイムに事故や順位変更情報を得られる本システムは、レースの新たな楽しみ方を提供できるものであったといえる。
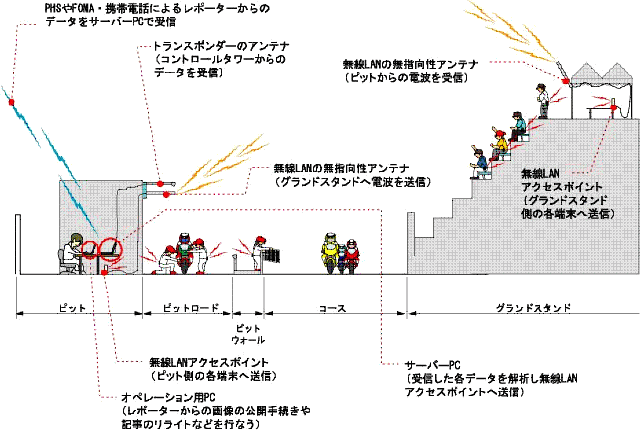 |
| 図2-2 バイクレースサポートシステムの概要 |
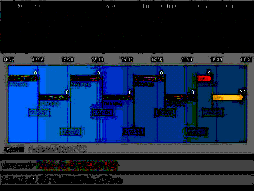 |
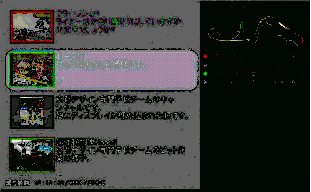 |
| 図2-3 戦略立案画面 | 図2-5 掲示板画面 |
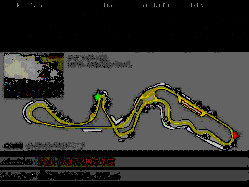 |
 |
| 図2-4 コース画面 | 図2-6 システムを利用している様子 |
また、その他の実運用例として、万博公園のナビゲーションシステムを作成した。1970年に大阪府吹田市で開催された大阪万国博覧会は、世界各国から6421万人を集めた史上最大級のイベントであった。その跡地は約260haの面積をもつ万博記念公園として整備され、パビリオンの跡地には記念プレートが設置されている。そこで、公園のバリアフリー化に関するシンポジウム「サイバーコミュニケーション2004」に協力する形で、健常者・身障者を問わずさまざまな人々が当時のパビリオンの姿を閲覧できる万博公園ナビゲーションシステムを開発した。提案システムは、GPSと地磁気センサを用いたウェアラブルシステムで、ユーザがパビリオン跡に近づいて、パビリオンのあった方向を向いたときに自動的にその場所に応じた説明がシースルーのHMDを通して再生され、さらにクイズなどのアミューズメントコンテンツや現在地の提示を行う。ハードウェアは誰でも操作が簡単に行えるように専用のボタンデバイスを製作し、PC本体は小型のリュックに入れて参加者に背負ってもらった。また、コンテンツおよびデバイス構成はユーザによって異なり、全盲のユーザにはヘッドフォンで音声案内を流し、聾唖者にはHMDで手話ビデオを流すといった方法を採用した。図2-7に示すシステムの表示例は、左上から「ナビゲーション矢印」「クイズ」「パビリオン説明」「現在地」をそれぞれ表示している。コンテンツはナビゲーション、クイズ、解説を含め60個作成し、1時間程度のナビゲーションを行えるようにした。
提案システムを、身体障害者20人を含む100人程度の人々に実際に利用してもらった。システムを利用している様子を図2-8に示す。アンケート結果より、いちいちガイドブックをめくるのではなく、その場に立ったら自動的に案内が出てくる受動的なナビゲーションシステムは、新たな公園案内の形態を実現しており有効であることがわかった。一方、全盲の被験者向けに音声ナビ、聾唖者向けにHMD上での手話ビデオナビといったように適応的にナビゲーション手法を切り替えたが、全盲の被験者はナビゲーションシステムのヘッドセットが耳を覆ってしまうことでかえって不都合が多くなるなど、視覚を補う聴覚、聴覚を補う視覚という考え方ではシステムが受け入れられないことがわかった。このように、大量の環境情報を受信する場合、いかに人間の活動を邪魔せずに情報を提示するかについてより詳細な検討が必要である。
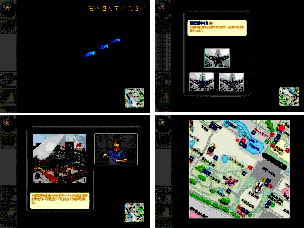 |
| 図2-7 ナビゲーションシステムの表示例 |
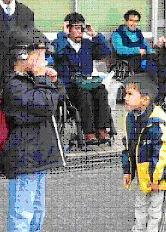  |
| 図2-8 ナビゲーションシステムを利用している様子 |
このようにシステムを実際に運用するに当たっては、システムの異常動作の検出やセキュリティなど、安全性に関する検討が重要となる。そこで本年度は、アプリケーションを構成するルール群が無限ループなどの異常動作を起こさないようにするための枠組みである動的トリガグラフ構築機構や、ウェアラブルコンピューティング環境においてユーザの状況に応じて動的にアクセス権限を変更するSBAC (Situation Based Access Control) に関する研究を行った。動的トリガグラフ構築機構では、ルールの実行関係を有向グラフで表現することで、システム内にあるルール群の安全性を評価する仕組みである。また、SBACは、アプリケーションを構成するルールそれぞれがもつ役割に応じてアクセス権限を定め、ユーザの移動などの状況変化に応じてアクセス権限を変更することで、悪意のある外部アクセスからプライベートなデータを守りつつ、場所に応じたさまざまなサービスを受けることが可能となる。
このように、本研究課題では基盤技術の開発とシステムの実運用を並行して進めることで、ウェアラブルコンピューティングによる新たなコミュニティ形成に関する研究を進めている。上に示したシステム以外にも、日常会話支援やデータ共有支援など、ウェアラブルコンピューティングを活用した実践的なシステムを多数構築している。
関連発表論文
(1) 宮前 雅一,寺田 努,岸野 泰恵,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“ウェアラブル環境のためのイベント駆動型ナビゲーションプラットフォーム”, 情報処理学会論文誌 (2005).(2) 宮前 雅一,寺田 努,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“ウェアラブルコンピューティング環境のための状況依存アクセス制御機構”, 電子情報通信学会論文誌 (2005).
(3) Masakazu MIYAMAE, Tsutomu TERADA, Masahiko TSUKAMOTO, and Shojiro NISHIO, “Design and Implementation of an Extensible Rue Processing System for Wearable Computing”, Proc. of the 1st Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems (MobiQuitous 2004), pp. 392--400 (Aug. 2004).
(4) Masakazu MIYAMAE, Tsutomu TERADA, Masahiko TSUKAMOTO, Keisuke HIRAOKA, Takahito FUKUDA, and Shojiro NISHIO, “An Event-driven Wearable System for Supporting Motorbike Races”, Proc. of the 8th IEEE International Symposium on Wearable Computers (ISWC '04), pp. 70--76 (Oct. 2004).
(5) Nga Viet PHAM, Tsutomu TERADA, Masahiko TSUKAMOTO, and Shojiro NISHIO, “An Information Retrieval System for Supporting Casual Conversation in Wearable Computing Environments”, Proc. of 5th International Workshop on Smart Appliances and Wearable Computing (IWSAWC 2005) (June. 2005, to appear).
(6) 寺田 努,“ユビキタスとウェアラブル環境/映像情報端末”, 映像情報メディア学会誌,Vol. 59, No. 1, pp. 16-20 (Jan. 2005).
(7) 三浦 直樹,宮前 雅一,寺田 努,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“ウェアラブルコンピューティング環境におけるメールを用いたP2P型情報共有システム”, 情報処理学会シンポジウムシリーズ マルチメディア,分散,協調とモバイルシンポジウム(DICOMO2004)論文集,pp. 489-492 (July 2004).
(8) ファン ガ ベト,寺田 努,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“ウェアラブル計算環境における会話連動型ウェブ検索システム”, ヒューマンインタフェースシンポジウム2004論文集(CD-ROM) (Oct. 2004).
(9) 宮前 雅一,寺田 努,塚本 昌彦,平岡 圭介,福田 登仁,西尾 章治郎,“バイクレース支援のためのイベント駆動型ウェアラブルシステム”, 情報処理学会研究報告(モバイルコンピューティングとユビキタス通信研究会 2004-MBL-29),Vol. 2004,No. 44,pp. 53-58 (May 2004).
(10) 宮前 雅一,岸野 泰恵,寺田 努,塚本 昌彦,平岡 圭介,福田 登仁,西尾 章治郎,“ウェアラブルコンピュータを用いた万博記念公園ナビゲーションシステムの設計と実装について”, 情報処理学会研究報告(モバイルコンピューティングとユビキタス通信研究会 2004-MBL-30),Vol. 2004,No. 95, pp. 1-8 (Sep. 2004).
(11) 宮前 雅一,寺田 努,岸野 泰恵,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“ウェアラブル環境のためのイベント駆動型ナビゲーションプラットフォームについて”,情報処理学会研究報告(ユビキタスコンピューティングシステム研究会 2004-UBI-6),Vol. 2004,No. 112,pp. 51--58 (Oct. 2004).
(12) 寺田 努,“農業・音楽・レース・司会 ~ ウェアラブル/ユビキタスシステムの実運用”, ヒューマンインタフェースシンポジウム2004 パネルセッション「現実の実感に向けて:あなたはデバイス派それともインタラクション派?」 (Oct. 2004).
4.10 ユビキタスコンピューティングを実現するイベント駆動型小型デバイスに関する研究
あらゆる物にコンピュータが埋め込まれ、それぞれが互いに通信しあいながら多様なサービスを提供するユビキタスコンピューティング環境に対する注目が高まっている。我々は、このようなユビキタスコンピューティング環境を実現するため、ルールベースの小型コンピュータであるAhroDを提案している。図2-9に示すAhroDはその動作をECAルールと呼ぶ動作記述言語で記述するため、ルールを入れ替えることでさまざまな用途に利用可能である。また、機能をできるだけシンプルに抑えることで小型化・軽量化・低コスト化を実現している。 |
| 図2-9 AhroDの外観 |
これまではAhroDの基本設計およびプロトタイプデバイスの開発を行ってきたが、本年度はAhroDを実運用するにあたって起こりうる問題を解決するための取り組みを行った。まず、実際に柔軟なシステムを構築できるようにするため、図2-10に示すような各種のアタッチメントを構築した。これらはセンサやボタンなどの入力デバイス、ブザーやLEDなどの出力デバイス、Bluetoothや赤外線などの通信ユニットを含み、入出力および通信方式を自由に組み合わせてユビキタスシステムが構築できる。
 |
| 図2-10 各種デバイス |
また、実際にAhroDを使った応用システムとして、Visual MarkerとAhroDを組み合わせた情報提供システム(図2-11)、RF-IDと組み合わせた入退室管理システム、壁面用ピン型デバイスと組み合わせた電子掲示システムなど多数のシステムを構築し、AhroDを用いることでさまざまなユビキタスアプリケーションを構築できることを示した。特に図2-11に示すピン型デバイスとの連携は、英国ランカスター大学のPin&Playプロジェクトと共同研究を行い、小型デバイスを用いた新たなサービス提供手法を提案した。さらに、AhroDを用いたストリームデータ処理手法およびネットワークトポロジ発見手法を提案し、小型デバイスを組み合わせることで高度な処理も実現可能であることを示した。
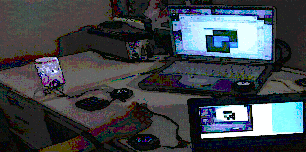 |
| 図2-11 Visual MarkerとAhroDの融合システム |
 |
| 図2-12 壁面用ピン型デバイス |
関連発表論文
(1) Tsutomu TERADA, Masahiko TSUKAMOTO, Keisuke HAYAKAWA, Tomoki YOSHIHISA, Yasue KISHINO, Shojiro NISHIO, and Atsushi KASHITANI, “Ubiquitous Chip: a Rule-based I/O Control Device for Ubiquitous Computing”, Proc. of 2nd International Conference on Pervasive Computing (Pervasive 2004), pp. 238--253 (Apr. 2004).(2) Yasue KISHINO, Tsutomu TERADA, Masahiko TSUKAMOTO, and Shojiro NISHIO, “A Ubiquitous Computing Environment Composed by Cooperation between Visual Markers and Event-Driven Compact Devices”, Proc. of the 1st International Workshop on Ubiquitous Data Management (UDM2005) (Apr. 2005, to appear).
(3) Tomoki YOSHIHISA, Yasue KISHINO, Tsutomu TERADA, Masahiko TSUKAMOTO, Ryohei SAGARA, Teruki SUKENARI, Daigo TAGUCHI, and Shojiro NISHIO, “A Rule-Based RFID Tag System Using Ubiquitous Chips”, Proc. of the 3rd International Conference on Active Media Technology (AMT2005) (May 2005, to appear).
(4) 寺田 努,“ユビキタスコンピューティング環境構築のための入出力制御デバイス”, 人工知能学会誌,Vol. 19, No. 4, pp. 410--417 (July 2004).
(5) 岸野 泰恵, 寺田 努, 塚本 昌彦, 義久 智樹, 早川 敬介, 柏谷 篤,西尾 章治郎,“イベント駆動型入出力制御デバイスのためのネットワークトポロジ発見手法”, 情報処理学会研究報告(ユビキタスコンピューティングシステム研究会 2004-UBI-5),Vol. 2004,No. 66,pp. 49--56 (June 2004).
(6) 寺田 努,塚本 昌彦,祐成 光樹,田口 大悟,“ユビキタス環境構築のためのイベント駆動型小型デバイスAhroD”, 電子情報通信学会2005年総合大会 (Mar. 2005,発表予定).
(7) 祐成 光樹,義久 智樹,田口 大悟,寺田 努,塚本 昌彦,柏谷 篤,西尾 章治郎,“イベント駆動型小型デバイスAhroDのためのBluetooth無線通信ユニットの開発”, 電子情報通信学会2005年総合大会 (Mar. 2005,発表予定).
(8) 義久 智樹,塚本 昌彦,寺田 努,岸野 泰恵,祐成 光樹,田口 大悟,西尾 章治郎,“イベント駆動型小型デバイスAhroDによるストリームデータ処理手法”, 電子情報通信学会2005年総合大会 (Mar. 2005,発表予定).
(9) 岸野 泰恵,寺田 努,塚本 昌彦,義久 智樹,祐成 光樹,田口 大悟,西尾 章治郎,柏谷 篤,“イベント駆動型小型デバイスAhroDのための通信エラーを考慮したトポロジ発見手法”, 電子情報通信学会2005年総合大会(Mar. 2005,発表予定).
(10) 相良 亮平,義久 智樹,岸野 泰恵,寺田 努,塚本 昌彦,祐成 光樹,田口 大悟,西尾 章治郎,“イベント駆動型小型デバイスAhroDのためのアプリケーション開発環境”, 電子情報通信学会2005年総合大会 (Mar. 2005,発表予定).
(11) 岸野 泰恵,寺田 努,Nicolas Villar,Hans-Werner Gellersen,“壁面を利用したピン型入出力デバイスのためのカメラを用いた位置検出手法”, 情報処理学会研究報告(ユビキタスコンピューティングシステム研究会 2005-UBI-7)(Mar. 2005,発表予定).
4.11 コミュニティにおけるコンテンツ管理を実現する情報フィルタリング・問合せ処理技術に関する研究
ウェアラブル・ユビキタス技術を用いて新たなコミュニティの形成が行われると、そのコミュニティ上でさまざまなデータ流通が行われることになる。そこで、そのようなデータ流通を円滑に行うために、さまざまな環境における情報フィルタリングおよび問合せ処理技術に関する研究を行った。まず、情報フィルタリングの新たな枠組みとして、フィルタリングを関数として定義し、さまざまなフィルタリング手法の性質を関数が満たす条件として表現するフィルタリング関数を提案し、その枠組みを用いた情報フィルタリングシステムの構築を行った。構築した情報フィルタリングシステムは、単一の端末でフィルタリングを行う際に、どのような順序でフィルタリング処理を行うべきかを計算し、動的に最適な処理手法を選択的に実行する機能をもつ。また、複数端末を用いた協調フィルタリング手法では、コミュニティ全体でのフィルタリング処理コストが最小になるようなフィルタリングの分配手法を提案した。提案するフィルタリングシステムを用いることで、環境の変化に合わせて常に最適なフィルタリング手法を選択できる。
また、端末同士が直接接続する環境であるP2P型システムや、放送型システムなど今後一般に広まるであろうネットワーク形態における問合せ処理方式を提案している。これらの方式は、さまざまな環境において従来の方式と比べて平均待ち時間や問合せ成功率を改善しており、次世代のネットワークシステムにおける効率的な問合せ処理を実現している。
関連発表論文
(1) Takuya KODERA, Rie SAWAI, Tsutomu TERADA, Masahiko TSUKAMOTO, and Shojiro NISHIO, “An Information Filtering System that Optimizes the Processing Method Based on Mathematical Properties”, Proc. of IASTED International Conference on Communications, Internet, and Information Technology (CIIT 2004), pp. 274--279 (Nov. 2004).(2) Hidekazu MATSUNAMI, Tsutomu TERADA, and Shojiro NISHIO, “A Query Processing Mechanism for Top-k Query in P2P Networks”, Proc. of the 1st International Student Workshop on Databases (SWOD 2005) (Apr. 2005, to appear).
(3) 小寺 拓也,澤井 里枝,寺田 努,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“情報フィルタリングシステムにおける待ちデータ数を考慮した処理方法変換方式”, 情報処理学会シンポジウムシリーズ マルチメディア,分散,協調とモバイルシンポジウム(DICOMO2004)論文集,pp. 539--542 (July 2004).
(4) 松波 秀和,寺田 努,西尾 章治郎,“P2P型コンテンツ検索システムにおける効率的なTop-k検索処理手法”, 電子情報通信学会第16回データ工学ワークショップ(DEWS2005)論文集 (Mar. 2005).
(5) 北島 信哉,寺田 努,原 隆浩,西尾 章治郎,“放送型データベースシステムにおけるモバイルクライアントのための問合せ処理方式”, 情報処理学会研究報告(放送コンピューティング研究グループ 2005-BCCgr-10), Vol. 2005, No. BCCgr-10, pp. 1--8 (Jan. 2005).
(6) 蔡 菁,寺田 努,原 隆浩,西尾 章治郎,“A Hybrid Approach of Broadcast Data Delivery and On Demand Wireless Communication”, 情報処理学会研究報告(放送コンピューティング研究グループ 2005-BCCgr-10), Vol. 2005, No. BCCgr-10, pp. 9--16 (Jan. 2005).
4.12 屋外における音楽活動を支援するシステムに関する研究
近年、ゲームセンターなどのアミューズメント施設では音楽系ゲームが大流行している。音楽系ゲームは能動的に音楽を発信するという新しい音楽の楽しみ方を提供しており、このようなアプリケーションの重要性は今後もますます高まってくると思われる。また、これらの音楽系ゲームは一般の人だけでなく、実際の楽器の演奏を得意とするミュージシャンをもゲームセンターに取り込むほどの流行を見せた。特にコナミ社の「ドラムマニア」や「キーボードマニア」は、それぞれドラムやキーボードの演奏方法がほぼそのまま取り入れられており、得意とする楽器の腕前を一般に披露する機会を与えている。また、これらのゲームは複数人でのプレイが可能であり、音楽的なコラボレーション(セッション)の場を提供する役割をもっている。このように、能動的に音楽を楽しみ、人に演奏を披露し、さらに他人と音楽でコラボレーションしたいという要求は非常に高くなっているが、現状では限られた場所でしかこのような機会が与えられていない。そのため、いつでもどこでも携帯型の楽器を用いて音楽を楽しみたいという要求が高まっている。そこで、本研究課題ではこれまでにPDAを用いた屋外向け楽器や、小型ゲーム機を用いたコード入力システムなどを構築することで、いつでもどこでも楽器を演奏できる環境を実現してきた。本年度は特に携帯型鍵盤楽器に着目し、持ち歩き可能な小型鍵盤において演奏性を損なうことなく音域の広い楽曲を演奏できる仕組みを考案した。
構築した鍵盤楽器であるモバイルクラヴィーアを図2-12に示す。モバイルクラヴィーアは従来の鍵盤楽器と異なり、すべての白鍵間に黒鍵を挿入した鍵盤楽器である。音域を移動させる場合、この黒鍵の色をON/OFFすることで、視覚的に現在設定されている音域を把握できるようにした。一般に、楽曲は数オクターブの音域を必要とするものが多いが、提案方式を用いることで2オクターブ程度の小型鍵盤を用意しておけばそのような広音域の楽曲を演奏できる。したがって、ピアノ演奏者がいつでもどこでも小型鍵盤を持ち歩き、自分の腕前を披露できるようになる。屋外で道行く人たちと即興演奏を行なう本システムのようなアプリケーションは、今後のモバイルアプリケーションの大きな柱となる可能性を秘めていると考えられる。
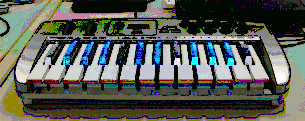 |
| 図2-13 モバイルクラヴィーアの外観 |
関連発表論文
(1) 竹川 佳成,寺田 努,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“音域分割機能をもつ小型鍵盤楽器モバイルクラヴィーアIIIの設計と実装”, 日本ソフトウェア科学会第12回インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ(WISS2004)論文集,pp. 65--70 (Dec. 2004).(2) 竹川 佳成,寺田 努,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“鍵盤を用いたPC用入力インタフェースの設計と実装”, 情報処理学会研究報告(音楽情報科学研究会 2004-MUS-55),Vol. 2004,No. 41,pp. 27--32 (May. 2004).
(3) 竹川 佳成,寺田 努,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“追加黒鍵をもつ小型鍵盤楽器モバイルクラヴィーアIIの設計と実装”, 情報処理学会研究報告(音楽情報科学研究会 2004-MUS-56),Vol. 2004,No. 56,pp. 83--88 (Aug. 2004).
(4) 竹川 佳成,寺田 努,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“歌唱機能をもつ黒鍵追加型小型鍵盤楽器モバイルクラヴィーアIVの設計と実装”, 情報処理学会研究報告(音楽情報科学研究会 2004-MUS-57),Vol. 2004,No. 111,pp. 101--106 (Oct. 2004).
(5) 竹川 佳成,寺田 努,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“音域分割機能をもつ小型鍵盤楽器モバイルクラヴィーアIII”, 日本ソフトウェア科学会WISS2004,デモ発表 (Dec. 2004).
5 社会貢献に関する業績
5.1 教育面における社会貢献
5.1.1 学外活動
NPO法人ウェアラブルコンピュータ研究開発機構の理事を務め、本法人が主催する各種の講演会、イベントにおいてウェアラブルコンピュータの普及啓蒙活動を行った。特に、2004年10月20日~23日に東京ビッグサイトで開催されたWPC EXPO2004において、ブース展示およびメインステージにおけるショーを行い、ウェアラブルシステムおよびユビキタスシステムの最新成果をIT関係者および一般客に紹介した。(寺田) |
| 図2-14 展示の様子 |
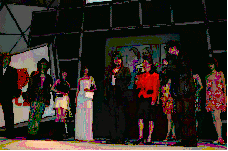 |
| 図2-15 ショーの様子 |
5.1.2 研究部門公開
2004年度いちょう祭・大学祭
2004年4月の銀杏祭、および11月の大学祭において、図学CAD教室(大学教育実践センターB棟3F)の外部公開を行った。午後1時から4時の間、パネル展示コーナーとCAD装置に実際に触れて演習や立体視を体験できるコーナーを開設した。(阿部)5.2 学会活動
5.2.1 国内学会における活動
(1) 日本建築学会建築教育委員会、教育と資格制度小委員会委員(阿部)(2) 日本図学会本部役員、理事(阿部)
(3) 情報処理学会ユビキタスコンピューティングシステム研究会、ヒューマンインタフェース研究会、エンタテインメントコンピューティング研究会、放送コンピューティング研究グループおよび日本バーチャルリアリティ学会エンタテインメントVR研究委員会の運営委員を務める。ユビキタス、放送という今後の日本における情報環境を担う研究活動を推進している。また、エンタテインメント分野では日本のリーダーシップが期待されており、まずは国内においてエンタテインメント研究を盛り上げるための活動を行っている。学会の運営委員としての活動以外では、第一回ウェアラブルコンピューティング研究会プログラム委員長、情報処理学会エンターテインメントコンピューティング2005プログラム副委員長を務めている。その他、マルチメディア、分散、協調とモバイル(DICOMO2004)シンポジウム実行委員、情報処理学会インタラクション2005プログラム委員、電子情報通信学会データ工学ワークショップ2005プログラム委員を務める。(寺田)
5.2.2 論文誌編集
(1) 日本図学会学会誌編集委員(阿部)5.2.3 国際会議への参画
以下の国際会議の運営に参画し、国際的な学術交流のために貢献している。(1) International Symposium on Network and Center-Based Research for Smart Structures Technologies and Earthquake Engineering, 2004.7の運営委員及びセッションの座長を務めた。(阿部)
(2) The 5th International Workshop on Smart Appliances and Wearable Computing (IWSAWC 2005) においてプログラム委員長を務め開催に貢献した。また、The Seventh International Conference on Ubiquitous Computing (UbiComp'05) ではポスターセッション委員長、2006 IEEE International Conference on Mobile Data Management(MDM 2006) ではローカルアレンジ委員長、The 2005 International Conference on Pervasive Systems and Computing (PSC-05) ではプログラム副委員長を務め、それぞれ会議の運営に貢献した。その他、The 11th International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS 2005),The 4th International Conference on Entertainment Computing (ICEC'05) および the 2005 IFIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (EUC-05) においてプログラム委員を務める。(寺田)
5.2.4 学会における招待講演・パネル
寺田 努,“農業・音楽・レース・司会 ~ ウェアラブル/ユビキタスシステムの実運用”, ヒューマンインタフェースシンポジウム2004 パネルセッション「現実の実感に向けて:あなたはデバイス派それともインタラクション派?」 (Oct. 2004).5.2.5 招待論文
該当なし5.2.6 学会表彰
寺田 努,2003年度電子情報通信学会論文賞 (2004).5.3 産学連携
5.3.1 企業との共同研究
塚本 昌彦,寺田 努,“ユビキタス情報提供基盤”, 日本電気株式会社インターネットシステム研究所 連携ラボ.西尾 章治郎,寺田 努,“状況・ユーザ嗜好による情報フィルタリング・提示技術の開発”, 三菱電機株式会社先端技術総合研究所との共同研究.
5.3.2 学外での講演
該当なし5.3.3 特許
該当なし5.4 プロジェクト活動
寺田 努,特定非営利活動法人ウェアラブルコンピュータ研究開発機構 理事.5.5 その他の活動
5.5.1 競争的資金の獲得
寺田 努(研究分担者),“大規模な仮想空間システムを構築する放送型サイバースペースに関する研究”, 日本学術振興会科学研究費補助金 基盤(B),5,000千円.2004年度研究発表論文一覧
著書
該当なし学会論文誌
(1) スーカン チッパンニャー,河本 順子,阿部 浩和,吉田 勝行,“ラオス及びタイ中北部におけるテラワダ仏教寺院の平面構成要素”, 日本建築学会,日本建築学会計画系論文集No582号, pp41-16, 2004.8(2) 阿部 浩和,吉田 勝行,“建築設計図面に対する見積指摘内容と設計変更内容の関連”,日本建築学会,日本建築学会計画系論文集No.581号,pp49-54, 2004.7
(3) パタナ ポンティップ,河本 順子,阿部 浩和,吉田 勝行,“ヴィエンチャン市における集合住宅の現状と住まい方”,日本建築学会,日本建築学会計画系論文集,No.585号, pp.1--8, 2004.11
(4) 阿部 浩和,吉田 勝行,“設計演習の初期段階における具体化のプロセスに関する一考察”,日本建築学会,第5回建築教育シンポジウム論文集,pp.81-86,2005.1
(5) 宮前 雅一,寺田 努,岸野 泰恵,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“ウェアラブル環境のためのイベント駆動型ナビゲーションプラットフォーム”, 情報処理学会論文誌 (2005).
(6) 宮前 雅一,寺田 努,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“ウェアラブルコンピューティング環境のための状況依存アクセス制御機構”, 電子情報通信学会論文誌 (2005).
国際会議会議録
(7) Sitthivan Somchith, Anolac Vira, Abe Hirokazu,“Laotian Visualization Ability for Architecture”, Proceeding of The 11th International Conference on Geometry and Graphics, pp.274-278,August 2004.(8) Hirokazu Abe, Somchith Sitthivan, Kensuke Yasufuku and Katsuyuki Yoshida,“Application of New Method for Graphic Science Education”, Proceeding of The 11th International Conference on Geometry and Graphics, pp.293-298,August 2004.
(9) Tsutomu TERADA, Masahiko TSUKAMOTO, Keisuke HAYAKAWA, Tomoki YOSHIHISA, Yasue KISHINO, Shojiro NISHIO, and Atsushi KASHITANI, “Ubiquitous Chip: a Rule-based I/O Control Device for Ubiquitous Computing”, Proc. of 2nd International Conference on Pervasive Computing (Pervasive 2004), pp. 238--253 (Apr. 2004).
(10) Masakazu MIYAMAE, Tsutomu TERADA, Masahiko TSUKAMOTO, and Shojiro NISHIO, “Design and Implementation of an Extensible Rue Processing System for Wearable Computing”, Proc. of the 1st Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems (MobiQuitous 2004), pp. 392--400 (Aug. 2004).
(11) Masakazu MIYAMAE, Tsutomu TERADA, Masahiko TSUKAMOTO, Keisuke HIRAOKA, Takahito FUKUDA, and Shojiro NISHIO, “An Event-driven Wearable System for Supporting Motorbike Races”, Proc. of the 8th IEEE International Symposium on Wearable Computers (ISWC '04), pp. 70--76 (Oct. 2004).
(12) Takuya KODERA, Rie SAWAI, Tsutomu TERADA, Masahiko TSUKAMOTO, and Shojiro NISHIO, “An Information Filtering System that Optimizes the Processing Method Based on Mathematical Properties”, Proc. of IASTED International Conference on Communications, Internet, and Information Technology (CIIT 2004), pp. 274--279 (Nov. 2004).
(13) Yasue KISHINO, Tsutomu TERADA, Masahiko TSUKAMOTO, and Shojiro NISHIO, “A Ubiquitous Computing Environment Composed by Cooperation between Visual Markers and Event-Driven Compact Devices”, Proc. of the 1st International Workshop on Ubiquitous Data Management (UDM2005) (Apr. 2005, to appear).
(14) Hidekazu MATSUNAMI, Tsutomu TERADA, and Shojiro NISHIO, “A Query Processing Mechanism for Top-k Query in P2P Networks”, Proc. of the 1st International Student Workshop on Databases (SWOD 2005) (Apr. 2005, to appear).
(15) Tomoki YOSHIHISA, Yasue KISHINO, Tsutomu TERADA, Masahiko TSUKAMOTO, Ryohei SAGARA, Teruki SUKENARI, Daigo TAGUCHI, and Shojiro NISHIO, “A Rule-Based RFID Tag System Using Ubiquitous Chips”, Proc. of the 3rd International Conference on Active Media Technology (AMT2005) (May 2005, to appear).
(16) Nga Viet PHAM, Tsutomu TERADA, Masahiko TSUKAMOTO, and Shojiro NISHIO, “An Information Retrieval System for Supporting Casual Conversation in Wearable Computing Environments”, Proc. of 5th International Workshop on Smart Appliances and Wearable Computing (IWSAWC 2005) (June. 2005, to appear).
口頭発表(国内研究会など)
(17) 田口 ゆか, 阿部 浩和,“住民意識から見た都市景観の構成に関する研究‐姫路市を事例として‐”,2004年度日本建築学会近畿支部研究報告集,第44号・計画系,pp.753--756,2004.6(18) Sitthivan Somchith,河本 順子,阿部 浩和,“ルアンプラパンの歴史的遺産保存地区におけるPSMVの現状と課題”,2004年度日本建築学会近畿支部研究報告集,第44号・計画系,pp.821--824、2004.6
(19) 田口 ゆか,阿部 浩和,“住民意識から見た都市景観の構成に関する研究―姫路市を事例として―”,2004年度日本建築学会(北海道)学術講演論文集,No.7504,2004.8
(20) Boutdakham Thanomxay, 阿部 浩和,“総合衛生管理製造過程(HACCP)が適用される食品工場の建築計画に及ぼす影響”,2004年度日本建築学会(北海道)学術講演梗概集,No5135,2004.8
(21) 安福 健祐,阿部 浩和,山内 一晃,吉田 勝行,“避難シミュレーションシステムの開発と地下空間浸水時の避難に対する適用性”,2004年度日本建築学会(北海道)学術講演梗概集,No5425,2004.8
(22) 安福 健祐,阿部 浩和,吉田 勝行,“リアルタイムCGによる汎用可視化システムの開発― マルチエージェント型建築避難シミュレーションへの適用 ―”,2004年度日本図学会本部例会学術講演論文集,2004.12
(23) 山内 一晃,阿部 浩和,“大手総合建設会社の新社 員に対する建築設計教育の概要”,2004年度日本図学会本部例会学術講演論文集,2004.12
(24) SITTHIVAN SOMCHITH, 阿部 浩和,“ラオス人の空間認識力に関する研究”,日本図学会関西支部例会学術講演論文集,2005.2
(25) 安福 健祐,阿部 浩和,吉田 勝行,“汎用可視化システムの開発とVR装置への適用性”,日本図学会関西支部例会学術講演論文集,2005.2
(26) 三浦 直樹,宮前 雅一,寺田 努,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“ウェアラブルコンピューティング環境におけるメールを用いたP2P型情報共有システム”, 情報処理学会シンポジウムシリーズ マルチメディア,分散,協調とモバイルシンポジウム(DICOMO2004)論文集,pp. 489--492 (July 2004).
(27) 小寺 拓也,澤井 里枝,寺田 努,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“情報フィルタリングシステムにおける待ちデータ数を考慮した処理方法変換方式”, 情報処理学会シンポジウムシリーズ マルチメディア,分散,協調とモバイルシンポジウム(DICOMO2004)論文集,pp. 539--542 (July 2004).
(28) ファン ガ ベト,寺田 努,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“ウェアラブル計算環境における会話連動型ウェブ検索システム”, ヒューマンインタフェースシンポジウム2004論文集(CD-ROM) (Oct. 2004).
(29) 竹川 佳成,寺田 努,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“音域分割機能をもつ小型鍵盤楽器モバイルクラヴィーアIIIの設計と実装”, 日本ソフトウェア科学会第12回インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ(WISS2004)論文集,pp. 65--70 (Dec. 2004).
(30) 松波 秀和,寺田 努,西尾 章治郎,“P2P型コンテンツ検索システムにおける効率的なTop-k検索処理手法”, 電子情報通信学会第16回データ工学ワークショップ(DEWS2005)論文集, (Mar. 2005).
(31) 竹川 佳成,寺田 努,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“鍵盤を用いたPC用入力インタフェースの設計と実装”, 情報処理学会研究報告(音楽情報科学研究会 2004-MUS-55),Vol. 2004,No. 41,pp. 27--32 (May. 2004).
(32) 宮前 雅一,寺田 努,塚本 昌彦,平岡 圭介,福田 登仁,西尾 章治郎,“バイクレース支援のためのイベント駆動型ウェアラブルシステム”, 情報処理学会研究報告(モバイルコンピューティングとユビキタス通信研究会 2004-MBL-29),Vol. 2004,No. 44,pp. 53--58 (May 2004).
(33) 岸野 泰恵, 寺田 努, 塚本 昌彦, 義久 智樹, 早川 敬介, 柏谷 篤,西尾 章治郎,“イベント駆動型入出力制御デバイスのためのネットワークトポロジ発見手法”, 情報処理学会研究報告(ユビキタスコンピューティングシステム研究会 2004-UBI-5),Vol. 2004,No. 66,pp. 49--56 (June 2004).
(34) 竹川 佳成,寺田 努,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“追加黒鍵をもつ小型鍵盤楽器モバイルクラヴィーアIIの設計と実装”, 情報処理学会研究報告(音楽情報科学研究会 2004-MUS-56),Vol. 2004,No. 56,pp. 83--88 (Aug. 2004).
(35) 宮前 雅一,岸野 泰恵,寺田 努,塚本 昌彦,平岡 圭介,福田 登仁,西尾 章治郎,“ウェアラブルコンピュータを用いた万博記念公園ナビゲーションシステムの設計と実装について”, 情報処理学会研究報告(モバイルコンピューティングとユビキタス通信研究会 2004-MBL-30),Vol. 2004,No. 95, pp. 1--8 (Sep. 2004).
(36) 竹川 佳成,寺田 努,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“歌唱機能をもつ黒鍵追加型小型鍵盤楽器モバイルクラヴィーアIVの設計と実装”, 情報処理学会研究報告(音楽情報科学研究会 2004-MUS-57),Vol. 2004,No. 111,pp. 101--106 (Oct. 2004).
(37) 宮前 雅一,寺田 努,岸野 泰恵,塚本 昌彦,西尾 章治郎,“ウェアラブル環境のためのイベント駆動型ナビゲーションプラットフォームについて”,情報処理学会研究報告(ユビキタスコンピューティングシステム研究会 2004-UBI-6),Vol. 2004,No. 112,pp. 51--58 (Oct. 2004).
(38) 北島 信哉,寺田 努,原 隆浩,西尾 章治郎,“放送型データベースシステムにおけるモバイルクライアントのための問合せ処理方式”, 情報処理学会研究報告(放送コンピューティング研究グループ 2005-BCCgr-10), Vol. 2005, No. BCCgr-10, pp. 1--8 (Jan. 2005).
(39) 蔡 菁,寺田 努,原 隆浩,西尾 章治郎,“A Hybrid Approach of Broadcast Data Delivery and On Demand Wireless Communication”,情報処理学会研究報告(放送コンピューティング研究グループ 2005-BCCgr-10), Vol. 2005, No. BCCgr-10, pp. 9--16 (Jan. 2005).
(40) 寺田 努,塚本 昌彦,祐成 光樹,田口 大悟,“ユビキタス環境構築のためのイベント駆動型小型デバイスAhroD”, 電子情報通信学会2005年総合大会 (Mar. 2005,発表予定).
(41) 祐成 光樹,義久 智樹,田口 大悟,寺田 努,塚本昌彦,柏谷 篤,西尾 章治郎,“イベント駆動型小型デバイスAhroDのためのBluetooth無線通信ユニットの開発”, 電子情報通信学会2005年総合大会 (Mar. 2005,発表予定).
(42) 義久 智樹,塚本 昌彦,寺田 努,岸野 泰恵,祐成 光樹,田口 大悟,西尾 章治郎,“イベント駆動型小型デバイスAhroDによるストリームデータ処理手法”, 電子情報通信学会2005年総合大会 (Mar. 2005,発表予定).
(43) 岸野 泰恵,寺田 努,塚本 昌彦,義久 智樹,祐成 光樹,田口 大悟,西尾 章治郎,柏谷 篤,“イベント駆動型小型デバイスAhroDのための通信エラーを考慮したトポロジ発見手法”, 電子情報通信学会2005年総合大会 (Mar. 2005,発表予定).
(44) 相良 亮平,義久 智樹,岸野 泰恵,寺田 努,塚本 昌彦,祐成 光樹,田口 大悟,西尾 章治郎,“イベント駆動型小型デバイスAhroDのためのアプリケーション開発環境”, 電子情報通信学会2005年総合大会 (Mar. 2005,発表予定).
(45) 岸野 泰恵,寺田 努,Nicolas Villar,Hans-Werner Gellersen,“壁面を利用したピン型入出力デバイスのためのカメラを用いた位置検出手法”, 情報処理学会研究報告(ユビキタスコンピューティングシステム研究会 2005-UBI-7) (Mar. 2005,発表予定).
解説・その他
(46) 寺田 努,“ユビキタスコンピューティング環境構築のための入出力制御デバイス”, 人工知能学会誌,Vol. 19, No. 4, pp. 410--417 (July 2004).(47) 寺田 努,“農業・音楽・レース・司会 ~ ウェアラブル/ユビキタスシステムの実運用”, ヒューマンインタフェースシンポジウム2004 パネルセッション「現実の実感に向けて:あなたはデバイス派それともインタラクション派?」 (Oct. 2004).
(48) 寺田 努,“ユビキタスとウェアラブル環境/映像情報端末”, 映像情報メディア学会誌,Vol. 59, No. 1, pp. 16--20 (Jan. 2005).
2004年度特別研究報告・修士論文・博士論文
博士論文
該当なし修士論文
(49) Boutdakham Thanomxay,“ヴィエンチャン特別市における戸建住宅の間取りと居住者意識に関する研究”, 大阪大学大学院工学研究科 修士学位論文, 2005.2卒業研究報告
(50) 川内 秀治,“都心部における建築物の地下鉄接続形態に関する研究 ‐バリアフリーの観点から‐”, 大阪大学工学部 卒業研究報告, 2005.2(51) 勝良 康次郎,“大学キャンパスにおける屋外広場の利用実態と学生の意識に関する調査・研究 -大阪大学豊中キャンパスを事例として-”, 大阪大学工学部 卒業研究報告, 2005.2
(52) 川内 秀治,“新大阪駅改造計画 ‐Parasitic Conversion‐”, 大阪大学工学部 卒業制作, 2005.2
(53) 勝良 康次郎,“underground city”, 大阪大学工学部 卒業制作, 2005.2