大学におけるプレゼンテーション能力の育成 - 情報教育の観点から
菅井 勝雄(大学院人間科学研究科 人間科学専攻)
(sugai@hus.)
山城 新吾(大学院人間科学研究科 D3)
(yamasiro@hus.)
(sugai@hus.)
山城 新吾(大学院人間科学研究科 D3)
(yamasiro@hus.)
1.はじめに
近年、情報教育は小・中・高校などの学校教育ばかりでなく、高等教育機関としての大学をも射程に入れ、重要視されるようになってきた。また、大学における改革の一環として、授業評価がほとんどの大学で試みられるようになったことにみられるように、指導法への注目もなされるようになってきた。こうした動きの中で、大学教育におけるプレゼンテーション能力の育成は、教える側の教師にとっても、また学ぶ側の学生にとっても、今や必須のものとなったといって過言ではない。そこで、本稿では、日常的に教育工学から情報教育の研究を進めている、筆者らが共同でこのプレゼンテーション能力をめぐって、少し理論的に論じてみることにしたい。また後者の山城はティーチング・アシスタントの経験も豊かであり、具体的な提案も試みる。
2.なぜプレゼンテーション能力か
情報化、国際化、環境問題などがまさに地球的な規模で進行している。こうした時代に生きていくには、かつてのように、「われ思う、故にわれ在り」を基準とする生き方では、もはや間に合わず、新たな「われコミュニケーションする、故にわれ在り」を基準とするような生き方が必要であるとする主張が、人間科学の中でなされている(Gergen,K.J.,1994)。それは社会的構成主義(social constructionism)と呼ばれ、このようなグローバルな課題への対応をめざしている。その理論的な指導者の一人であるガーゲンは、過日人間科学部を訪れ、講演を行った。対人的なコミュニケーションを介したそのような課題への取り組みを常に考えていることもあってか、その講演は英語でなされたものの、適切に身振りや手振りも入って、きわめて理解しやすく学生にも好評であり、さすがと思わせるものであった。
つまり社会的構成主義では、情報化、国際化、環境問題などは相互依存の関係にあって、これらに立ち向かって生きるには、個人が個人主義的に引きこもってしまったのでは対処できず、むしろ対人的なネットワークの関係性の中で、自己と他者とのコミュニケーションに参加し、議論したり、調整するなど、協力して問題を解決し、また学習して知識を社会的に構成していくことを主張する。
まだ記憶に新しい、前世紀の情報化社会がもたらした「2000年問題」は、諸外国の人々の参加と協力による、世界規模での問題解決の象徴的な例であったといえる。
このような考えのもとでは、自己と他者(グループ)とのコミュニケーションにおいて、他者との理解を図るため自己を適切に「表現」すること、すなわちプレゼンテーション能力の育成が要請されてくることになる。
近年、学校教育においても、こうした能力やスキルの育成が図られているのは周知の通りであるが、とくに情報教育では情報技術(IT)や情報通信技術(ICT)を用いた取り組みがなされ始めている。ここで述べた考え方に、この種の技術が適合するように進んできたことにもよる。これらについては後述する。
3.教師のプレゼンテーション
教育工学の歩みを振り返ってみると、はじめの頃は「教師のプレゼンテーション」が注目されたといえる。今日、大学における講義法とも教育方法上関連するので、きわめて簡単に触れてみよう。認知心理学者のブルーナーは、かつて表象系モデルを提唱した(Bruner,J.S.,1966)。それは表1に示すものである。
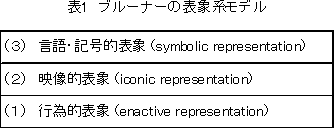
このモデルでは、人間の認識水準には3種類あるとする。それらが行為的、映像的、言語・記号的な各表象として示される水準である。そのうち、(1)の行為的表象では、認識は行為や活動の水準でなされる。したがって、この水準での認識や理解のためには、行為や活動を通して、また身振りや手振りなどに訴えることが必要となってくる。同様に(2)の映像的表象では、認識は映像の水準でなされる。そこで、この水準での認識や理解のためには、映像すなわち静止画、動画、絵などを用いて、イメージに訴えることが必要である。(3)の言語・記号的表象では、認識はシンボルである言語や記号などの水準でなされる。この水準での認識や理解のためには、そうしたシンボルに訴えることになる。
ブルーナーは、このように当時の認知心理学において、表象理論(representation theory このrepresentationは「表現」と訳されることに注意。人工知能では knowledge representation「知識表現」と訳される)に立脚して、このモデルを提示したのである。その意味では、これはプレゼンテーションの理論モデルでもある。
これまで学校教育では、大筋においてではあるが、教師はこのモデルのもとに学習指導することを促されてきたといってよい。つまり、小学校の低学年では (1)の行為的水準、続いて学年が進むと (2)の映像的水準で、絵などを用いてのプレゼンテーションによってである。教科書にも「さし絵」が多用される。そして高学年になると、言語や数学の記号を駆使するプレゼンテーションへ進むという具合である。このように、そのモデルは発達段階説に合わせる形でも用いられた。
しかし、大学における指導では、教師はこれら3種のすべてにわたって注意を払い、プレゼンテーションを行うべきであろう。
その後、提唱者のブルーナー自身、発達段階説に無理に押し込める必要のない一般的なモデルであることを主張している。確かに、たとえば「ネクタイの結び方」を教えるといった卑近な例を考えても、「ネクタイの結び方は・・・」と言葉で説明しながら、それにネクタイを首に巻いて結んでいく動作や行為を伴わせて、映像的に提示してやるというようなプレゼンテーションがわかりやすい。この場合、3種のすべてが必要なのであって、そのうちのどれが欠けても、相手に理解させ学習に導くことは困難であろう。
とりわけ、外国人が相手のコミュニケーションでは言葉が異なるので、各種の映像的装置を用いたり、行為的な身振りや手振りなどが多用されることになろう。
近年、マルチメディア型のコンピュータが登場し、このモデルが示す3種の表象系がほぼすべて取り扱えるようになってきた。プレゼンテーション支援の強力な装置が登場したわけで、国際学会などでもPowerPointなどのプレゼンテーション用ソフトウェアが多用されるようになってきた。
4.学生のプレゼンテーションの指導
学校における情報教育では、教師側よりもむしろ学習者側のプレゼンテーションの指導へと比重が移ってきている。それは既に触れたような理由もあるが、自己表現用の「お絵描き」ソフト、ワープロソフトなどの普及や、WorldWideWeb、電子メールなど、マルチメディア、インターネットが導入されはじめたことによる。まさしく情報ネットワーク時代の、自己と他者とのコミュニケーションに必要なプレゼンテーション能力の育成が目指されるようになったわけである。このことは、大学においても例外ではあり得ず、学生のプレゼンテーション能力やスキルの育成を目指す指導が不可欠であることを示している。現在、人間科学部一回生を対象に開講されている「情報活用基礎」では、受講生が3名程度のグループに分かれ、いくつかのトピックの中からひとつを選択、グループが調べた成果をApplixプレゼンテーションを用いて講師およびクラスの他の受講者に発表する実習が行われている。2000年度の同様の実習の結果を受け、2001年度は習熟度別にクラス分けされた学生がプレゼンテーションの実習に取り組んでいる(Nakamuraほか,2001)。扱われるトピックは教官グループがあらかじめ準備しており、「高速ネットワーク時代」の回を例にあげると、ブロードバンドネットワークについて世界の高速通信事情を調べ、韓国や台湾と比較して日本が立ち遅れた理由を挙げなさい、など、合計16個のトピックがあり,毎回4グループが発表を行っている。
ティーチング・アシスタントとしてこれまでの授業でのプレゼンテーションを見た限りでは、文字の見やすさ、背景やアニメーション機能の活用などプレゼンテーションの見栄えもさることながら、各グループとも扱うトピックの概要や、検索サイトなどを駆使して調べた成果を発表し、更に自らの問題意識に基づいてトピックを深く掘り下げるなど、大学院のゼミでも十分通用するような素晴らしい内容のプレゼンテーションを行ったグループもあった。
では、これからの可能性として、プレゼンテーション能力の幅を拡げる指導の提案を行う。
5.「仲間うち」を超えたプレゼンテーション
「説明は聞いたけど、やっぱりよく分からない」自分がよく知っている事柄を説明するのでも、仲間相手では自分の意図した通りに理解してもらえるのに、興味・関心や専門の違う人に説明しようとすると、途端に困難に直面した経験は、誰もが持っているのではないだろうか(筆者も先日、コンピュータに触れたことのない親から「Linuxって何?」と訊かれ、どこから説明しようかと悩んだ)。社会的構成主義に関連した議論の中でも、Bronfenbrenner(1978)が提唱する、学習環境における生態学的視点への関心が高まっている(菅井ほか,2000)。しばしば教室の中だけに限定されがちな学習者を取り巻く環境について、地域コミュニティや社会制度などをも視野に入れて学習環境を拡張する考え方であり、図1がBronfenbrennerの示したモデルである。
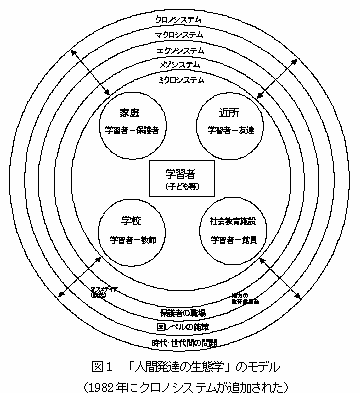
中心のミクロシステムは学習者の直接的な参加による経験の場、外側にあるメゾシステムは地域社会、エクソシステムは保護者の職場や地方行政などで、例えば転居でエクソシステムが大きく変わると、学習者もまた大きな影響を受ける。マクロシステムは文化や国家の政策、クロノシステムは時間枠にかかわり、世代間の問題に対処できるとされる。同心円の中核におかれる学習者、ならびに内側のシステムは、外側に位置する各システムの直接的ないし間接的な影響を受ける。
先のプレゼンテーション実習では、学習者は個人的な興味・関心の差はあるが、人間科学部の同じクラスというグループに属している。その場合これらの同心円は安定しているが、教室の外、例えば大学外での実習や遠隔共同学習などで異なる分野・関心をもつ人々と接する場合では、この同心円に変化が生じ、学習者が自らと環境への認識を再構成することが必要になってくる。「誰に、何を、どう説明するのか」。そのためには、説明する相手がどのような背景や関心を持っているかといった調査、説明にあたって前提知識とされていた概念を改めて説明するといった話題の再構成、相手が説明を理解しているかどうかの把握など、それぞれの学習者がより幅広い能力を磨くことが一層必要とされる。企業における顧客サポートも、「商品に応じた説明」だけでなく「顧客に応じた説明」が必要とされていると聞くが、このような訓練を大学時代に積んでおくことは有意義ではないかと思う。
参考文献
Bronfenbrenner,U. (1979) The ecology of human development : Experiments by nature and design.Harvard Uviversity Press.( 磯貝芳郎・福富護訳 (1996) 人間発達の生態学-発達心理学への挑戦.
川島書店.)
Bruner,J.S. (1967) Toward a instruction theory. Harvard University Press.
Gergen,K.J. (1994) Realities and Relationships. Harvard University Press.
Nakamura,M., Nakanishi,M. and Harada,A. (2001) Analysis of Grouping Strategy for Presentation
Exercise in Computer Literacy course. ITHET01,Kumamoto.
菅井勝雄・西森年寿・劉威 (2000) メディア利用の社会・文化的学習モデルの研究-理論的検討-.
教育工学関連学協会連合第6回全国大会講演論文集第二分冊, pp.705-706.