情報活用基礎におけるプレゼンテーション演習の導入
中村匡秀(サイバーメディアセンター情報メディア教育研究部門)
(masa-n@cmc.)
(masa-n@cmc.)
1. 概要
共通教育科目「情報活用基礎」の人間科学部対象のクラスにおいて、2000 年度からプレゼンテーション 用ソフトウェアを用いた発表演習を授業内容に導入している。授業対象は1回生であったが、学生の評判 はおおむね良く、自主的に勉強したという学生も多い。本稿では演習導入の目的、発表課題の内容、授業 の進め方などについて紹介する。以降では特に断らない限り、筆者が担当した2000 年度・人間科学部1 年対象「情報活用基礎」で行った プレゼンテーション演習について述べる。2000 年度の受講者は144 名であり、4 つのクラスに分けられ同 じ内容の授業が進められた[2]。筆者はそのうちの1 クラスを担当した。表3に2000 年度の全スケジュー ルを示す。なお、2001 年度においても同様の演習を進行中である。
2.演習導入の目的
2.1 情報活用の基礎としてのプレゼンテーション技術
「情報活用基礎」のようなコンピュータリテラシー科目では、ワープロや表計算などのソフトの使い方 や、メール・インターネットの操作法など、「パソコンの使い方」ばかりに重点が置かれる傾向にある。プ レゼンテーションは、コンピュータの操作技能に習熟する目的もあるが、むしろ、自分の力で情報を探索 し、理解した情報を他人に伝達する態度と方法を学ぶという意味で、情報教育に欠かせないものと考える。 現状では、大半の学生がプレゼンテーションの講義を受けることも無く、卒業論文発表などで初めて先輩 に教わるという例が少なくない。そこで、授業担当教官(中西、原田、田中、大崎、中村)で話し合った 結果, 情報活用の基礎としてのプレゼンテーション技術を講義に取り入れることにした。2.2 学生の授業参加への契機づくり
従来の教官から学生への一方通行の授業では、学生にとってはおのずと受身型の学習になってしまう。 学生は不明な点や質問事項がある場合でも挙手や質問をする雰囲気でもない。さらに、「情報活用基礎」で は各人に端末が与えられているので、講義を聴かずにWeb やメールに没頭する学生も少なからず存在す る。また、教官にとっても学生が学習上どういった点で苦労するかということをすべて正確に把握するこ とは困難で、学生側の疑問点・問題点に気付かず流してしまうこともある。そこで、学生に課題のみを与 え、教壇に立たせて学生の視点からどういう困難があったかも含めて説明させることで、学生に積極的に 授業に参加させる契機を作る。2.3 自己学習とコミュニケーション
最近では、情報関連のWeb のリソースや図書が無数に存在し、調査のための素材や資料は比較的容易に 入手できる。そこで、題材と関連資料に関するヒントのみを与え、あとは学生に自己学習・発表させるこ とで、学習の向上をはかる。また、学生同士の「教え合い」は教育効果があると考える。一つは学生同士 対等の立場から質問をしやすいことがある。同じような苦労・その解決法は学生同士共通であることが多 いからである。さらに質問に答える側は、相手に伝える際に問題の再認識や思考整理をせねばならず学習 になる。プレゼンテーション演習には、グループ学習を通してこうしたコミュニケーションを増進させる 効果が期待できる。3 実施内容
3.1 準備
2000 年度の受講生は人間科学部1 年生144 人であり、4 クラスに分けて、それぞれの教室で並列に講義 を行った。筆者が担当した第1 クラスは45 人であった。プレゼンテーションを行うにあたって、まず3 人ずつの15 の小グループに分けた。このグループ分けのポリシーはクラス毎に異なっている[4]。筆者の 担当した第1 クラスは、中間試験の結果を基に上位のものを各グループの軸とするようなグループ分けを 行った。 次に、プレゼンテーションの基礎の1 回分の講義を行った。決められた時間内にいかに相手に自分の考 えを伝えられるかについて、身近な例を挙げつつ講義を行った。また、発表の起承転結や発表練習の重要 性、発表のエチケットなどについてのプレゼンテーションを実演した。 さらに、情報教育計算機システムのプレゼンテーションソフト、Applix Presents についての講習を行っ た。学生達は以前の講義でドローソフト、Applix Graphics について習熟していたため、それほどの困難も 無く各自習得できたようである。3.2 課題
課題の選択においては、情報活用に関連する最近の話題で、かつコンピュータ分野における情報のみに 偏り過ぎないように配慮を行った。その結果、15 グループ分のトピックを以下のように決めた。| 第1回: | インターネットの検索サイト | 第2回: | 行政機関の情報公開 |
| ・様々な再確認や頭の整検索サイト ・検索エンジンの種類と特徴 ・情報検索のテクニック ・専門検索サイト |
・なぜ情報公開か ・情報公開に積極的な行政機関 ・インターネットを使った事例 ・世界との比較 |
||
| 第3回: | 情報倫理 | 第4回: | 人口問題と情報社会 |
| ・情報フィルタリング ・知的財産権 ・わいせつ情報 ・チェーンメール |
・日本社会の人口問題に付いて ・IT 革命 ・情報社会の不平等問題 |
3.3 実施形態
まず授業の最後に、次週のプレゼンテーション課題と担当グループを決める。課題を与えるにあたって は、課題に関連したいくつかのWeb サイトをヒントとして与えた。課題を与えられたグループは、次週の 講義までの1 週間で、調査、プレゼンテーションファイルの作成、発表練習を全てこなさなくてはいけな い。準備に当たっては、グループ内の3 人でOHP ファイル作り・調査・発表というような作業分担を行 うよう指導した。プレゼンテーションは、各グループ約7 分の持ち時間で、4 回の授業の後半時間に行った(表3、第11 ~14 回)。教育実習棟の教室は室内の端末が陰になるため、スクリーンとプロジェクタによる通常のプレ ゼンテーションの形式を実施することが難しい。従って、発表者には教室前の教官端末で操作させ、各端 末の間に配置してある補助モニタに映して発表させた。発表後は短い質問時間を設け、教官からの短いコ メントなども行った。
また、プレゼンテーションの評価を学生同士で行わせた。具体的には、発表したグループのプレゼンテー ションそれぞれに対して、感想・質問・アドバイスなどを各クラスのメーリングリストに投稿するという ものである。最後に,各グループにはプレゼンテーションのファイルを提出させた。これを、HTML 形式 に変換し「情報活用基礎」のホームページで公開することで、他グループのスライドの参考や復習が可能 となった。
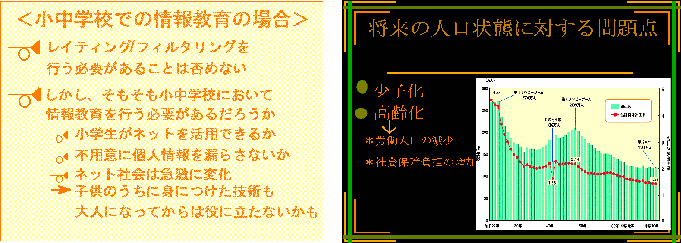
(a)情報フィルタリング (b)日本の人口問題
図1:学生のスライド
4 評価
筆者自身からの主観的評価によれば、どのグループも自分たちなりにわかりやすくまとめようとしてい る努力が見られたと思う。図1 に学生達が作ったプレゼンテーションスライドの例を挙げる。色やグラフ、 表などを効果的に取り入れて、オリジナリティを出そうとしていたグループもあった。また、グループ内 のコミュニケーション不足がまれに見られた。スライド担当者が趣向を凝らしたOHP を作成してきたに もかかわらず、発表担当者が当日になって内容を知って練習無しの発表を行い、聴講者に意図が良く伝わ らなかったグループもあった。 次に、学生からの客観的評価についてである。期末試験時(表3、第16 回)に、全学生に対して「情報 活用基礎」に関する習熟度アンケートを行った[1]。そのアンケートの中から、プレゼンテーション演習に 関する10 の質問とその答えを表2に示す。有効解答数は135 であった。表中の質問1 から6 は演習そのも のについて、7 から10 はグループ作業についての項目になっている。各質問に対して、答えは「そう思わ ない」から「そう思う」まで、1 から5 までの5段階評価を行わせ、全クラスの平均と標準偏差を示して いる。どの質問についてもおおむね中央値3 を超える評価を得ている。特に、「1. 与えられたテーマは適切で あった」、「5. プレゼンテーション演習は価値がある」、「6. 今後も情報活用基礎で行うべきである」の項目 がスコアが高かった点から、プレゼンテーション演習導入は成功であったと考えている。
5 反省点など
「情報活用基礎」は1 セメスタ分しかなく、プレゼンテーションだけでなく、表3にあるような、他の 様々な事柄もカバーしなければならない。そのため、プレゼンテーションに割ける時間がどうしても限ら れてしまう。発表時間も7 分しかなく、質問にいたっては1 分も割けなかった。そのためか、発表後の学 生からの質問はほとんどなかった。この質疑応答の訓練もやりたかったが、今回の授業ではそれができな かった。今後の重要な課題である。| NO. 質問内容 | 全クラス平均 | 標準偏差 |
| 1 与えられたテーマは適切であった 2 発表および議論の時間は十分であった 3 学生同士の評価コメントは有用であった 4 テレビのニュース画面構成に興味を持つようになった 5 プレゼンテーション演習は価値がある 6 今後も情報活用基礎で行うべきである 7 グループ分けは適切であった 8 グループ内の意見交換は十分に出来た 9 自分はグループ内で十分貢献した 10 グループでの作業は楽しかった |
3.7 3.5 3.1 2.1 3.5 3.6 3.5 3.2 3.4 3.5 |
1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.3 1.3 1.1 1.2 |
同じく、時間の都合上であるが、各グループが1 回しか発表できなかったことも残念である。せめて2 回あれば、1 回目の発表後のいろんな声をフィードバックさせて、技術の向上になったことだろうと思う。
また、プロジェクタの代わりに補助モニタを使うことで、聴講者は目の前で内容を追うことが出来るが、 発表者に目がいかず、発表者と聴講者のアイコンタクトが出来なかったという問題もあった。
2001 年度の演習では学生にプレゼンテーション評価シートを配り、それぞれのプレゼンテーションを聴 講者のなお、2001 年度の演習では学生にプレゼンテーション評価シートを配り、それぞれのプレゼンテー ションを聴講者の視点から評価させている。視点から評価させている。
6 おわりに
2000 年度人間科学部1 年「情報活用基礎」で行ったプレゼンテーション演習について、目的、内容、評 価などについて述べた。先生から生徒への一方通行の授業に比べ、生徒に自主的に調査させ授業作りをさ せることの大切さがわかったような気がする。基礎工学部では、学生に自主的に学習を実施させる「PBL (Problem-Based Learning)」という科目を導 入している[3]。これは、1,2 回生の学生に課題だけ与え、教官は一切解答を与えず、学生のみのグループ 討論を通して、自主的に問題解決をさせるという授業である。情報科学科では、豊中市のボランティア団 体のホームページ起ち上げに貢献するなど、成果をあげている。今後の教育を考えるにあたって、文系理 系を問わず、こうした試みをどんどん取り入れていくことは重要ではないだろうか。
最後に、このプレゼンテーション演習に関する全ての情報は、http://webserver/?masa-n/j-kiso/ に公 開されている1。課題の詳細や学生のスライド等は、上記アドレスを参照されたい。また、グループ分けに よる学習効果の統計分析等も含め、プレゼンテーション演習の詳細報告を文献[4] にまとめている。ご興味 のある方は併せて参考にしていただきたい。
参考文献
[1] 中西:「情報処理教育科目における授業評価」、情報処理教育研究集会論文集、pp.512-515 (2000-12)[2] 原田、中西、中村、大崎、田中:「能力別クラス別編成とクラス間で均等にした編成の比較評価」、情 報処理教育研究集会論文集、pp.136-138 (2000-12)
[3] 齊藤, 都倉: 「ある創成科目の計画立案と実施状況?2 年生向け創成科目の事例」, 平成12 年度工学・ 工業教育研究講演会講演論文集, pp.287-290 (2000-7) 1サイバーメディアセンター教育用計算機システムからのみアクセス可
[4] Nakamura M., Nakanishi, M., Harada, A: “Analysis of Grouping Strategy for Presentation Exercise in Computer Literacy Course”, Proc. of Int’l Conf. on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET2001), CDROM (2001-7)
| 授業 | 日付 | 授業題目 | 内容 |
| 第1回 第2回 第3回 第4回 |
04/17/00 04/24/00 05/08/00 05/15/00 |
ログイン・ログアウト テキスト入力 電子メール ワープロ、作図ソフト |
授業の意義、利用マナー、パスワード配布、ログイン、 ログアウト、パスワード変更のし方、Netscape の使い方 gEdit の使い方、ファイル保存、タッチタイピング、 日本語変換、メールの初歩 メールのしくみ、ディスク容量、メールボックスの整理、 ファイルマネジャGMCによるファイル操作、情 報検索 Applix Word, Applix Graphics の使い方、文書整形、 画像の文書への貼りこみ、ペイントソフトGIMP |
| 第5回 第6回 第7回 第8回 |
05/22/00 05/29/00 06/05/00 06/12/00 |
ネットニュース これまでのまとめ 中間試験 ホームページ作成1 |
第4 回の復習、ネットニュースの使い方。質問投稿。 第1 回~第5 回までの総復習 文書整形、情報検索、タッチタイピング、日本語変換、 作図、エチケットなどに関する問題 HTMLの基礎、テキストエディタを用いた編集 、ペー ジの公開 |
| 第9回 第10回 第11回 第12回 |
06/19/00 06/26/00 07/03/00 07/10/00 |
ホームページ作成2 プレゼンテーション技術 プレゼン準備 OPAC、Web のしくみ プレゼン演習第1回 フロッピー、文字コード、 データ量 プレゼン演習第2回 |
色、画像の貼りこみ、リンク、ホームページ素材 プレゼンテーション演習の準備、グループ分け、発表 のし方、Applix Presents の使い方 図書の検索システムを使った情報活用、WWWの簡単 な原理、URL など センター端末のフロッピー操作、日本語コードの説明 と変換のし方、データ量の数え方 |
| 第13回 第14回 第15回 第16回 |
09/04/00 09/11/00 09/18/00 09/25/00 |
表計算1 プレゼン演習第3回 表計算2 プレゼン演習第4回 コンピュータのしくみ 期末試験 |
Applix Spread Sheet の使い方、データ入力、グラフの 書き方 関数を用いた計算、並べ替えなどのデータ整理、 テキストのインポート、エクスポート コンピュータのしくみについて概説、CPU、HDD、記憶装置 など、ホームページコンテストの結果 HTML、OPAC、文字コード、データ量、表計算、電子メール から出題 |