文学部『情報活用基礎』におけるプレゼンテーション実習の試み
北道淳司(サイバーメディアセンター情報メディア教育研究部門)
(kitamichi@cmc.)
(kitamichi@cmc.)
1.はじめに
文学部の学生を対象とした情報活用基礎の授業では、一年生の第一セメスタにおいて主に情報リテラシ の教育を行っている。本年度よりはじめて、プレゼンテーション実習を導入した。現在、実施している途 中ではあるが、その経緯について報告させて頂く。なお、文学部の情報活用基礎の授業は、文学部一年生180 名(さらに今年度は再履修の学生は13 名を含 む)に対し、3つの教室(豊中教育実習棟第1、第2、第3 教室)を利用して実施している。本稿では、特 に断らない限り、著者が担当している第2 教室(学生72 名、TA 2 名)における状況を述べる。
2.文学部情報活用基礎の概要
本授業では、一コマ90 分の授業を15 回行い、ログイン・ログアウト、かな漢字変換、エディタ、電子 メール、電子ニュース、WWW、ワープロ、ドロー・ペイントツール、ホームページの作成、LaTEX によ る文書作成等の学習項目を習得する。この授業では、教官が概要(概念、計算機の操作方法など)を説明しデモを行い、それに対して引き続 き学生は演習を行うという形態である。TA には、演習時に学生からの質問に応対してもらっている。
3.プレゼンテーション実習
本年度からは、LaTEX による文書作成の代りに、サイバーメディアセンター情報教育システム(Linux システム)で利用可能な『Applix プレゼンテーション』を用いたプレゼンテーションのためのスライド 作成および発表(質疑応答も含む)の実習を行うことにした。 現在、15 回の講義のうち12 回を終了、プレゼンテーション実習を行う7 回のうち5 回を終了したとこ ろである。3.1 目的
情報活用基礎では、コンピュータを利用して、情報を収集し、それらを整理・分析し、他者に伝達・発信 できるようになることを目的としている。特に他者への伝達・発信に関して、従来の文学部対象の情報活 用基礎のカリキュラムでは、電子メール・ニュース、ホームページ、ワープロ・LaTEX による文書作成な どが含まれているが、他者の前で自分の意見を発表する(話す、説得する、ディスカッションする)内容 は含まれていなかった。しかし、学生の将来においてグループミーティング等の場においてプレゼンテー ションを行う機会は今後ますます多くなることが予想されることなどから、プレゼンテーション実習を試 みることにした。プレゼンテーション実習前に学習しているワープロ、ドロー、ペイントツール、WWW上の検索エンジ ンを用いた情報検索を活用する総合演習的な課題として、有用であると考えるまた質疑応答などによるディ スカッションの練習、他者の発表の評価を行うことなども、プレゼンテーション実習の目的に含まれる。
3.2 実施方法
プレゼンテーション実習の日程は以下の通りである。スライド作成に用いるツールは、『Applix プレゼ ンテーション』である。これのサブセットであるドローツールの『Applix グラフィックス』、ワープロ、か な漢字変換などは習得済である。また、以下の授業では、ホームページ作成の説明・実習が並行して行わ れている。授業内容の末尾の数字は、90 分の授業時間に対して実際にプレゼンテーション実習に要した時 間の割合を示す。第1 回目 実習の概要の説明、テーマの提示(20%)
第2 回目 スライドの作成方法、プレゼンテーションの実行方法の説明(70%)
第3 回目 スライドの作成実習(30%)
第4 回目 スライドの作成実習, 次回発表者の決定(100%)
第5 回目 3 名発表、第6,7 回発表者の決定(100%)
第6 回目予定 6 名発表
第7 回目予定 6 名発表
第1 回目に、プレゼンテーション実習の概要について筆者がApplix プレゼンテーションを用いて説明し た。また、用意したテーマ(付録参照)を示し、それらの中から各学生にプレゼンテーションを行うテー マの希望を提出させた。
第2 教室では、学生一人一人がテーマに対して調査を行い、スライドを作成することにした。ただし、 発表は同じテーマを与えられた3、4 人の中で選ばれた一人が全員の前で発表することにした。他の教室で は、2~4 名程度のグループでのスライド作成を行わせ、全グループの発表を行わせることを予定している。
一つのテーマに対し4 人程度の学生を割り当て、第2 回目から第4 回目の授業および自習時間に、テー マに関するスライドと発表内容に関する資料を作成させた。資料は、スライドに掲載できないような、全 体の概要、各スライドの詳細あるいは補足説明、参考資料、要した作業時間などをまとめたものである。
第4 回目では、テーマ(1) OPACからテーマ(4) 携帯電話/ PHS のサービスまで割り当てられた学生の 間で、相互にスライドおよび資料を交換させ、互いに採点させた。それらの結果をもとに、同一テーマを 与えられた学生のなかで最高点を獲得した学生に、第5 回目の授業で発表させた。学生間での相互の採点 においては、スライドを実際に発表させることが望ましいが、時間の関係上、印刷されたスライドと資料 を交換しそれを各自読むことにより採点させた。
第5 回目では、発表すべき学生が一人欠席し、3 名の発表(発表約7 分、質疑応答約5 分)を行った。学 生には教室の教官卓の端末にログインさせ、プレゼンテーションを行った。質疑応答では、聴講している 学生にも質問を促したが、ほとんど教官あるいはTAが質問を行った。聴講する学生は、発表者毎にチェッ クシートに発表の採点を行い、感想をまとめ、教官に提出する。
9 月には、第6、第7 回目を予定しており、計12 名の発表を行う予定である。
3.3 検討すべき項目
本年度から実施したプレゼンテーション実習については、試行錯誤で進めているのが現状であり、検討 すべき項目は非常に多い。その中でいくつかを取り上げる。テーマ
テーマは、情報活用基礎に関連するテーマを教官が用意し、それらの中から選択させることにし た。中には、自ら興味のあるテーマについてまとめたいという学生もいたが、学生間の評価による発 表者の決定が困難になると考え、自由テーマは許可しなかった。 初めの4つのテーマは、(発表の時期が早いので)調査およびスライド作成が行いやすいように、あ る程度具体的でまとめ易そうなものを選んだ。
グループ分け
他の教室ではグループ発表を行っているが、筆者の担当教室では個人個人での資料作成とし た。これはグループ発表とすると、分担によっては、スライド作成をまったく行わないというような 場合も考えられ、全員が、資料収集、スライド作成を経験することを目標とした。また、グループ作 業の場合、グループ内での個人の負荷の違い、個人の評価の難しさ等の問題も考えられる。 第5 回目の授業の後(相互評価により発表者を決定した後)での学生の感想からは、他人のスライ ド・資料と比較できたことに関しては概ね、良い経験であったことが伺われる。
4.まとめ
プレゼンテーション実習をアナウンスした当初の学生からの反応としては、『人前で発表することは絶対 にいやである』という感想が多くあった。しかし、第5 回目の授業の後の感想では、スライドのまとめ方、 発表の仕方などに関して、多くの学生は他人のスライドおよび発表に興味を持っており、自分との比較に ついて述べている学生も多かった。実際学生が作成したスライドを図1 に示す。発表した3名のスライドは、作成時間の少なさからテキス トによる説明文が多かった。残りの発表では図形やグラフ等を利用したスライドを期待したい。
課題としては、第2 教室では個人ごと発表であるので、約1/4 の学生しか実際には発表できない。理想 的には、全員が発表すること、何度か発表を行いスライドおよび発表方法をブラッシュアップできる機会 を複数回与えられればよいが、時間および場所の関係で困難である。今後は、残りの12 名の発表を行い、 それらの経緯、収集したチェックシート等を解析し、グループ発表を行っている他教室との比較を行い、今 後の授業の参考としたい。
今回のプレゼンテーション実習では、すでに昨年度から実施されている人間科学部対象の情報活用基礎 の授業担当の先生方に多大な協力を頂いている。この場をお借りしてお礼を申し上たい。
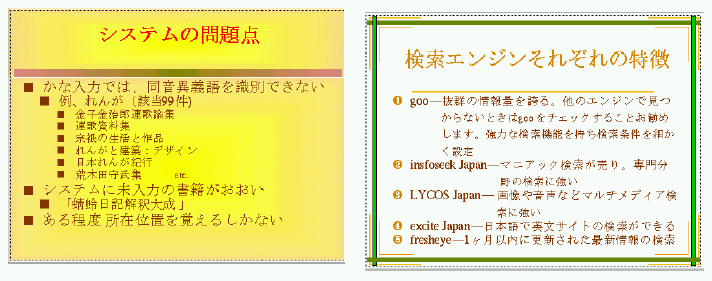
図1: テーマ1および2のスライドの一つ
付録プレゼンテーションテーマ一覧
(1)OPAC 大阪大学附属図書館のOPAC は、どのようなサービスが提供されているか、主なサービスの利用方法を 説明せよ(2) 検索エンジンの比較情 報教育システムのホームページのリンク集http://webserver/link.shtml の検索エンジン が提供するサービスを比較する
(3) 家庭とインターネット 例えば、家庭とインターネットを接続するにはどのような方式があって、それぞれどのよ うな特徴があるか
(4) 携帯電話/ PHS のサービス 例えば、現状の携帯電話/ PHS にはどのようなサービスが提供されているか、ま た、今後どんなサービスを期待するかなど
(5) インターネット時代の政治政治 (国会、政府、政党、裁判所)はどのようにインターネットを利用/活用してい るか、いくつかの団体に着目して事例を調べる。また、将来、どのような利用が考えられるかなど
(6) インターネット時代の行政 地方自治団体(都道府県、市町村)はどのようにインターネットを利用/活用してい るか、いくつかの団体に着目して事例を調べる。また、将来、どのような利用が考えられるかなど
(7) インターネット時代の学校 学校(大学、高校、中学など)はどのようにインターネットを授業、クラブ活動など に利用/活用しているかいくつかの学校に着目して事例を調べる。また、将来、どのような利用が考えられる かなど
(8) インターネット時代の医療 医療はどのようにインターネットを利用/活用しているか事例を調べる。また、将来、 どのような利用が考えられるかなど
(9) インターネット時代の防災 防災システム(国、地方公共団体、ボランティアグループなど)はどのようにインター ネットを利用/活用しているかいくつかの事例を調べる。また、将来、どのような利用が考えられるかなど
(10) インターネット時代の福祉 福祉(地方公共団体、ボランティアグループ、企業など)はどのようにインターネッ トを利用/活用しているかいくつかの事例を調べる。また、将来、どのような利用が考えられるかなど
(11) インターネット時代の図書館、美術館、博物館 図書館、美術館、博物館などの展示物を公開/維持保存してい る組織は、どのようにインターネットを利用/活用しているかいくつかの事例を調べる。また、将来、どのよう な利用が考えられるかなど
(12)IT 時代の著作権問題 WWW を利用してたくさんのホームページが閲覧できるが、それらのコンテンツに関し て著作権の問題が多く取り上げられている。実際の事件を取り上げて報告する
(13) ネット犯罪(サイバー犯罪) インターネットを利用してたくさんのサービスを受けらが、それを悪用した犯罪も 多発している。実際の事件を取り上げて報告する
(14) コンピュータウィルス メールなどを悪用して、コンピュータウイルスが多くの被害をもたらす事件が発生して いる。実際の事件を取り上げて報告する