2006年問題に対応した「情報活用基礎」の在り方について
清川清・中澤篤志(サイバーメディアセンター 情報メディア教育研究部門)
1.はじめに
高等学校の必修科目として新設された普通教科「情報」を履修した学生が、2006 年度からいよいよ入学してくる。この「2006 年問題」に対応するため、各大学では一般情報処理教育(文系・理系を問わない全学生に対する情報処理教育)の内容をどのように変革すべきかを検討している。本稿では、大阪大学の全学共通教育科目として開講されている「情報活用基礎」の現状と問題点を挙げ、2006 年問題への対応について考察する。
2.高校教科「情報」について
まず前提知識として、教科「情報」について簡単にまとめておく。1996 年7 月、中央教育審議会が「21 世紀を展望した我が国の教育の在り方」と題した答申の中で、情報社会に対応した教育の必要性を指摘した。その後、2 年の検討を経て、1998 年7 月の教育課程審議会の答申において、普通教科「情報」が新設されることが報告され、1999 年3 月29 日に当時の文部省から、高等学校学習指導要領が告示された[1]。教科「情報」の全体目標は次の3 つの観点にまとめられる!- 情報活用の実践力
課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含めて、必要な情報を主体的に収集・判断・表現・処理・創造し、受け手の状況などを踏まえて発信・伝達できる能力。 - 情報の科学的な理解
情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と、情報を適切に扱ったり、自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解。 - 情報社会に参画する態度
社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響を理解し、情報モラルの必要性や情報に対する責任について考え、望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度。
「情報A」は最も基礎的な構成であり、主に文書作成、表計算、ウェブページの作成、プレゼンテーションなどの演習(全体の1/2 以上の時間)を通じて情報活用の実践力を養成することに重点を置く。
「情報B」ではプログラミング、アルゴリズム、データベースなどの学習を通じて情報を科学的に理解させることに重点を置く。演習は全体の1/3 以上の時間を充てる。
「情報C」ではネットワークの仕組みやネチケットなどの学習を通じて情報社会を理解させ、情報活用の実践力と情報社会に参画する態度を養う。演習は全体の1/3 以上の時間を充てる。
ただし、これらの科目はすべてを必修とするのではなく、1 科目以上を学校選択で行う。また、主に情報教育を実施する人的な資源が不足しているため、実施内容・実施レベルについて高校間でのバラつきが大きいという問題点が指摘されている。こうした理由により、一口に必修科目「情報」を履修したといっても、生徒によって履修内容が大きく異なっている。従って、来春からの新入生の既得知識についても共通した前提を置きにくい状況となっている。
3.「情報活用基礎」の経緯と現状
3.1 経緯
1992 年に、文部省(当時)から情報処理学会への委嘱研究「一般情報処理教育の実態に関する調査研究」の報告書(大岩レポート)がまとめられ[2]、一般情報処理教育の具体的な実施案などが提案された1。同調査研究には基礎工学部情報工学科(当時) の都倉教授らが参画しており、大岩レポートを受けて、本学では1992 年11 月より本学における一般情報処理教育の必修化に関する検討を開始した。1993 年2 月1 日には、大岩レポートを踏襲しつつ、より現実的な表1 のような実施案を示した。この実施案に基づき、1994 年から「情報活用基礎」の講義が一部の学部で開始された。現在では、全学共通教育科目の情報処理教育科目として「情報活用基礎」以外に「コンピュータのしくみ」、「情報科学入門」、「情報社会と倫理」、「情報探索入門」、および「計算機シミュレーション入門」の5 科目が開講されている。
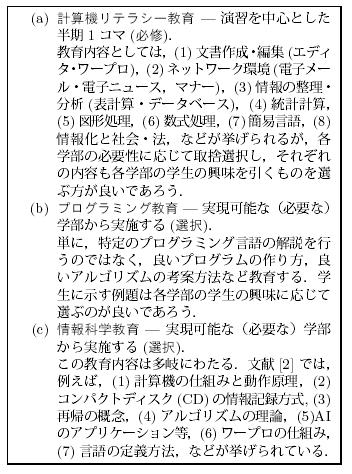 |
3.2 シラバス
2005 年度の全学共通教育科目シラバスによれば、「情報活用基礎」の授業の目的と計画、内容は表2 のように記述されている。多くの学部・学科では、このシラバスに基づいて講義内容を構成している。ただし、自由裁量に拠るところが大きいため、詳細は部局によって異なる。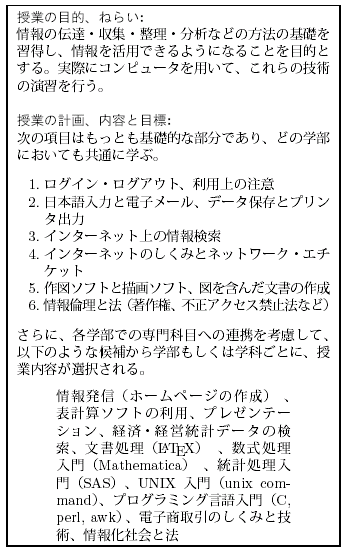 |
3.3 現状の問題点
以上を踏まえ、現状の「情報活用基礎」科目が抱える問題点を列挙する。3.3.1 教科「情報」との重複
1992 年の大岩レポートを踏襲した現状の「情報活用基礎」と、その後の1999 年に指導要領が示された高校科目「情報」の方向性は(ある意味では当然であるが)似通っている。特に最も履修者の多い「情報A」は、情報の様々な利活用を通じた実践力の養成、という点で「情報活用基礎」の目的と類似している。本来「情報活用基礎」では、さらに踏み込んで、様々な実習を通じて計算機の本質を理解し、新しい問題を自ら解決するための応用力を身につけることを志向している。しかし、演習主体の授業であるため、ややもすると個々のツールの利用方法などの「操作の習得」だけで手一杯になりがちである。これは、「情報活用基礎」のシラバスではなく教授法の問題とも言えるが、実態としては、同じく実習に比重を置く「情報A」と内容が重複している面がある。3.3.2 事前習熟度の差異
従来、筆者を含む多くの授業担当教員が、新入生の事前知識や事前習熟度に大きな幅があることを感じてきた。来年度からはこうした事前習熟度について一定の底上げがなされることが期待できる一方で、その上下差の幅が縮小されるかどうかは疑わしい。即ち、2 章の末尾で述べたような様々な理由により、新入生が習得している知識・技能の内容や習熟度には、引き続き大きな差異があると予想される。こうした習熟度の異なる学生への対応策として、文学部では一学年200 名弱の大所帯を習熟度別の3クラスに編成する方式を採用し一定の効果を上げている。しかしながら、クラス編成を要するほど受講生が多い学部・学科は限られており、同様の対応が不可能な部局も多い。事前習熟度の異なる多様な学生への対応について、さらに検討する必要がある。3.3.3 コマ数の不足
文献[2] では半期に換算して8 コマ分に相当する理想的な授業内容が示されていた。これに基づいて、本学の全学共通教育でも6 つの情報処理教育科目が実際に開講されているが、「情報活用基礎」を除いて2 必修科目ではなく受講生は限定されている。教科「情報」についても、3 科目それぞれに異なる意義があるが、ほとんどの高校では1 科目を扱うのみである。このように、本来大学生が素養として身につける意義のある情報処理教育は大変広範であるのに対し、実際に高校や本学で履修される内容は限定されている。それらすべての情報処理教育を大学教育において実施するには絶対的にコマ数が不足しているが、現状からの大幅なコマ数の増加は人的・設備的資源の点から現実的ではない。限られたコマ数で何を教えるべきか、十分に議論する必要がある。4.センターの立場
以上で「情報活用基礎」にまつわる2006 年問題の経緯と問題点を述べた。サイバーメディアセンター情報メディア教育研究部門としては、こうした問題への対応策を議論する必要性を訴え、そのための参考情報を提示し、実際に議論の場を提供し、最終的な合意形成を促すために主導的な役割を果たす責務がある。本節では、これらの点について述べる。4.1 議論の必要性
前節で述べたように、現状の「情報活用基礎」の在り方について何らかの見直しを要することは間違いない。しかしながら、具体的に何を教えるべきかは必ずしも明らかではない。これは、一つには来春以降の新入生の実態(特にバラつき具合)が現時点では不明であり、ある程度は推測で判断するよりないためである。具体的な授業内容を決定しにくいより重要な理由は、学部・学科によって立場や見解が異なることである。一部では、教科「情報」の登場に鑑みて「情報活用基礎」などの一部の情報処理教育科目はもはや不要であるといった声も聞かれる。しかし、計算機が日常的な道具として浸透すればするほど、個人の成長過程に合わせた情報処理教育を継続的に実施することがより重要になってくる。ましてや新入生の教科「情報」の履修内容は一律ではない。従って、大阪大学の学生が当然身に着けておくべき知識と技能を一定のベースラインとして定義し、統一的に実践する必要があるだろう。そのためにはシラバス見直しの必要性をできる限り多くの教員に認知していただき、具体的な見直しの中身について議論をしていただく必要がある。
4.2 授業内容の参考情報
具体的な授業内容として参考になる資料として、2006 年問題を踏まえて2000 年に文部科学省から情報処理学会に委嘱された調査研究がある。この最終報告書[3] では、「情報とコンピューティング」と「情報とコミュニケーション」という二つの中核的科目、およびプログラミング基礎や情報倫理などの補完的科目群が設定され、詳細な授業実施案が示されている3 。大まかには、「情報とコンピューティング」は「情報B」と、「情報とコミュニケーション」は「情報C」と、各々方向性が類似している。2006 年問題に対応した「情報活用基礎」の授業内容は、「情報とコンピューティング」および「情報とコミュニケーション」の内容から必要な項目を取捨選択して構成することが考えられる。例えば、現状の半期1 コマ体制を維持するとした場合、以下のような3 つの案が考えられる。.
- 両者を通年の1 コマとしてすべて実施する(現状よりコマ数が増える)
- 両者から項目を半分ずつ抜き出して半期の1 コマとして実施する
- 文系・理系に合わせていずれか1 科目のみを半期の1 コマとして実施する
また、こうした発展的内容を扱う場合、取り残される学生への対応策についても検討する必要があるかも知れない。その場合、基礎的な内容を講習会やe-Learning により対応することが考えられる。しかし、講習会の実施は人的コストが高く各部局の協力が不可欠である。一方、e-Learning は、WebCT をはじめサイバーメディアセンターでもその基盤整備を積極的に進めてきたところではあるが、コンテンツ制作を誰がどのように行うかという大きな問題があり、やはり容易には実現できない。こうした点も含めて、広く議論する必要がある。
4.3 活発な議論のために
具体的に議論を進める場として、一つには情報処理教育研究会4 を活用することができる。これは、従来サイバーメディアセンターが毎回情報処理教育に関するテーマを設定して一年に1~2 度、不定期に開催している研究会であり、情報処理教育に関心があれば誰でも自由に参加できる。この研究会を通じて、様々な意見を交換し、大阪大学の情報処理教育科目、特に「情報活用基礎」の在り方を議論いただくのがよいと考えている。次回は10 月中の開催を予定しており、「情報活用基礎」を実際に担当する授業担当教員の方々を中心に発表をしていただく予定で現在調整を進めている。今後は研究会開催の頻度を例えば2ヶ月に一回程度に高めて継続的に議論を進めていく必要があるだろう。こうした議論を踏まえて、実際のカリキュラム編成にあたっては、共通教育カリキュラム委員会の情報処理教育科目委員会が担当することになる。5.おわりに
「情報活用基礎」などの情報処理教育科目の在り方を検討するためには、できる限り多くの教員に積極的に議論に参加いただく必要がある。今後は活発な議論を促すために参考情報の調査・広報や研究会の開催に尽力していきたい。参考文献
| [1] | 文部科学省高等学校学習指導要領 第2 章 普通教育に関する各教科第10 節情報, http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/990301d/990301k.htm, 1999. |
| [2] | 「一般情報処理教育の実態に関する調査研究」(文部省委嘱調査研究), 情報処理学会,一般情報処理教育の実態に関する調査研究委員会(1992-03), 1992. |
| [3] | 「大学等における一般情報処理教育の在り方に関する調査研究」(文部科学省委嘱調査研究), 情報処理学会,大学等における一般情報処理教育の在り方に関する調査研究委員会(2002-03), 2002. |
1大岩レポートの概要と本学情報処理教育科目の変遷については、本特集の松浦・中西の稿を参照されたい。
2「情報活用基礎」も歯学部や法学部では選択となっている。
3これらの詳細は文献[3] もしくは、本特集の松浦・中西の稿を参照されたい。
4情報処理教育センター時代の1992 年度に開始された。